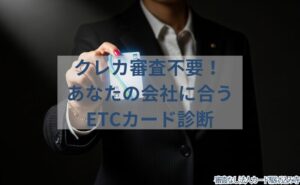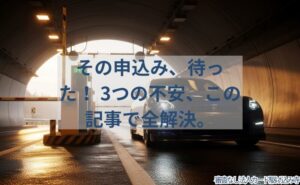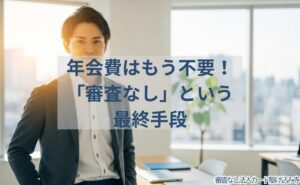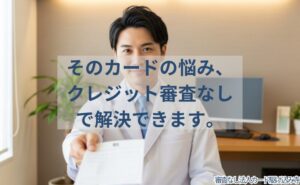この記事は約27分で読めます。
法人ETCカード作れない!審査なしで選ぶ最適解
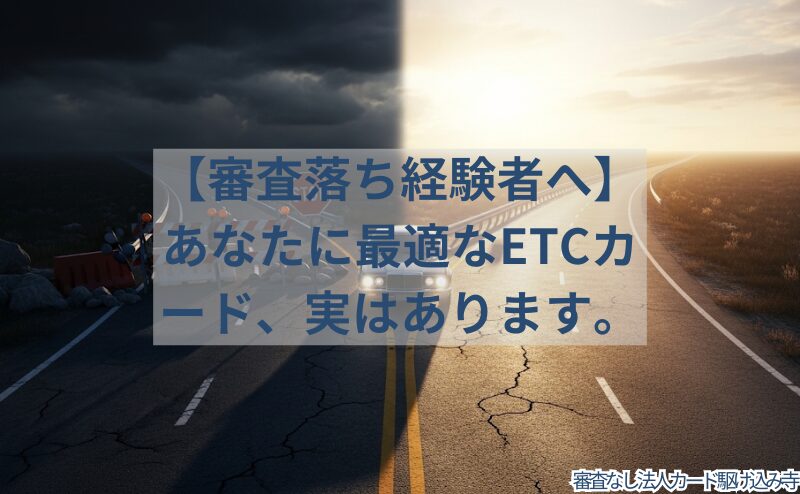
会社の設立、あるいは個人事業主としての独立、本当におめでとうございます。事業を軌道に乗せるため、日々忙しくされていることでしょう。しかし、事業用の車で高速道路を使う段になって、「あれ、法人ETCカードが作れない…」という壁にぶつかっていませんか?実はこれ、多くの経営者が経験する、本当に頭の痛い悩みなんです。
特に、設立間もない新設法人 ETCカードの発行は、会社の信用を証明する決算書がないため、審査が非常に通りにくいのが現実です。これは、事業に奮闘する個人事業主 ETCカードを探している方にとっても、決して他人事ではありません。私自身も会社を作った当初、意気揚々とメインバンクやネット系の法人カードに申し込んでは、「設立2年未満」という理由であっさり否決の通知を受け取り、途方に暮れた経験があります。
中でも、大口利用が前提のETCコーポレートカードは審査が特に厳しいことで知られており、我々のような中小零細企業や個人事業主には、正直なところ少しハードルが高いかもしれません。この記事では、そんな「法人ETCカードが作れない」という切実な悩みを抱えるあなたのために、状況別の最適な解決策から、審査なしでカードを作る具体的な方法、そして契約前に知っておくべき注意点まで、私の経験を余すところなくお伝えしていきます。
- 法人ETCカードが作れない、あなたの状況に合った最適な解決策が分かります
- なぜ「審査なし」でETCカードが作れるのか、その仕組みをスッキリ理解できます
- 代表的な2つの組合を客観的なデータで徹底比較し、あなたに合う1枚が見つかります
- インボイス制度への対応など、契約で失敗しないための実務的な注意点を知ることができます
【解決策】法人ETCカードが作れないあなたへ|状況別・最適な1枚
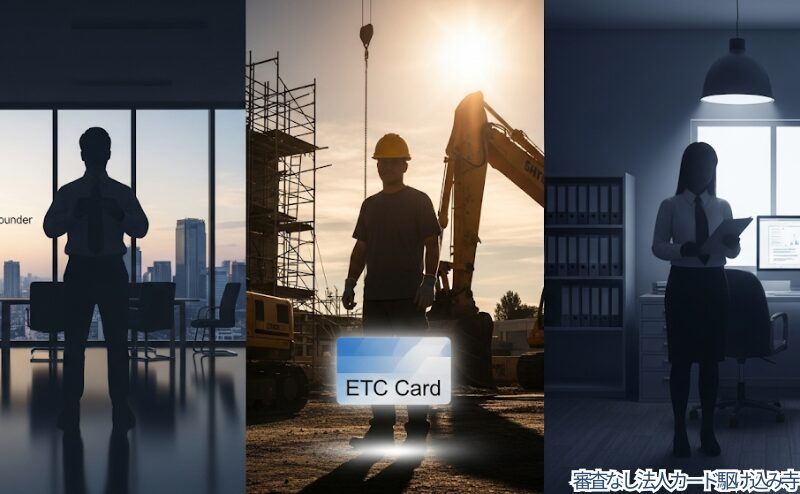
この章で解説する内容
- あなたはどれ?3つの状況で見る悩み
- 【創業者向け】新設法人ETCカードの最適解
- 【個人事業主向け】個人事業主ETCカードは手軽さ重視で選ぶ
- 経理担当者向けは信頼性と管理のしやすさ
- ETCパーソナルカードという選択肢もある
法人ETCカードが作れない、と言っても、その背景にある事情は本当に人それぞれです。会社の状況やあなたの立場によって、選ぶべきカードは微妙に変わってきます。まずはご自身の状況を客観的に見つめ直し、どの解決策が最もフィットするのか、一緒に考えていきましょう。
あなたはどれ?3つの状況で見る悩み
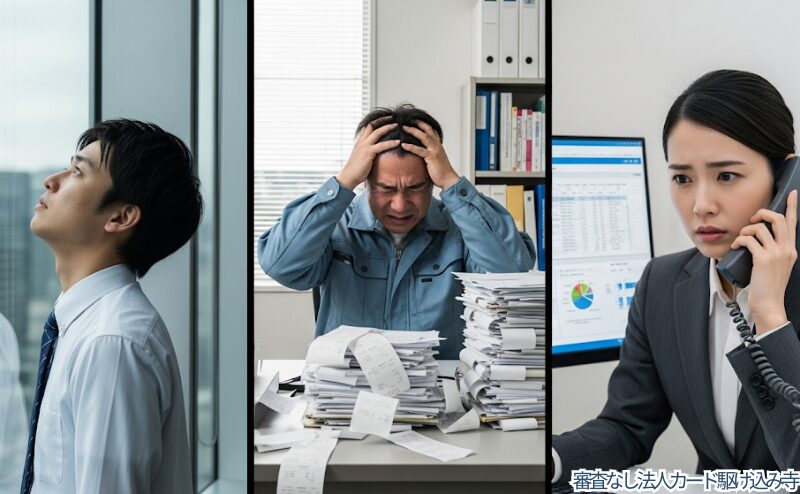
法人ETCカードが作れないという悩みは、本当に根が深いですよね。私自身もそうでしたし、周りの経営者仲間から話を聞いていても、その理由は人それぞれです。しかし、突き詰めると、その悩みは大きく3つの状況に分類できると私は考えています。
もしかしたら、あなたは今、この中のどれかに当てはまるのではないでしょうか。ご自身の状況を少しだけ客観的に見つめるような気持ちで、読み進めてみてください。
状況1:設立直後で、信用の壁に直面している創業者の方
「事業への情熱も計画もある。でも、会社にまだ事業実績(決算書)がない…。」
これは、創業期に誰もが経験する、最初の大きな壁かもしれません。実際に、中小企業白書などを見ても、創業時の課題として「資金調達」と並んで「社会的信用の不足」が常に上位に挙げられています。
税理士や金融機関の担当者からすれば、過去の実績がない以上、あなたの事業の将来性ではなく、あくまで「過去の実績に基づく返済能力」という画一的な基準で判断するしかありません。理屈では分かっていても、事業を前に進めるためのインフラが整わないことに、焦りや苛立ちを感じてしまうのは、当然のことだと思います。
この状況の本質は、あなたの価値が低いのではなく、既存の金融システムの物差しでは、まだあなたの価値を測れないという点にあります。
状況2:経理が苦手で、とにかく手軽さを求める個人事業主の方
「現場仕事で手一杯なのに、これ以上面倒な手続きは増やしたくない…。」
本業の腕には絶対の自信があるものの、事務作業はどうしても後回しになりがちで、確定申告のたびに税理士さんから経費の公私混同を指摘される…。職人気質の方に、本当に多いパターンだと感じます。
税理士が口を酸っぱくして事業用カードを勧めるのは、あなたを守るためです。税務調査の際に個人の支出と事業の経費が混在していると、それだけで調査官の心証を損ねるリスクがあるのです。経費管理の徹底は、節税以前の『防御』と言えるでしょう。
この状況の本質は、「面倒くさい」という感情の裏に、「追徴課税」や「信頼の失墜」といった事業上のリスクが隠れているという点です。
状況3:会社の財務状況に悩む経理担当者の方
「前期が赤字決算だった影響で、ETCカードの追加発行を断られてしまった…。」
これは、会社の番頭役として経理や総務を一手に担う方にとって、非常に頭の痛い問題でしょう。国税庁の統計によれば、実は日本企業の約6割が赤字決算というデータもあり、決して珍しいことではありません。
しかし、カード会社は常に「途上与信」といって、既存の取引先の信用力を定期的にチェックしています。赤字決算が続くと、それはあなたの会社への評価というより、カード会社自身のリスク管理プロセスの一環として、機械的に利用枠の削減や追加発行の停止といった措置が取られることがあるのです。
この状況の本質は、自社の努力だけではコントロールできない外部要因によって、事業に必要なインフラが脅かされるリスクを常に抱えている点にあります。
 筆者
筆者どうでしょう。一つでも「あ、自分のことだ」と感じるものはありましたか?
もしあったなら、ご安心ください。どの扉の先にも、必ず光は射しています。それぞれの状況に合わせた、確かな解決策がちゃんと存在するのですから。
【創業者向け】新設法人ETCカードの最適解


会社を立ち上げたばかりの方が、最初にぶつかる大きな壁。それが、法人ETCカードをはじめとする、クレジットカードの審査です。
結論から申し上げますと、協同組合が発行する法人ETCカードが、創業期の経営者にとって、現時点で最も合理的で賢明な最適解です。この章では、なぜ私がそう断言できるのか、その理由を私の経験も交えながら詳しくお話しします。
創業者が審査に落ちやすい「本当の理由」
私自身もそうでしたが、設立して1年未満、つまり最初の決算を迎えるまでは、事業の実績を客観的に証明するものが何もない状態と言えます。
多くのクレジットカード会社では、申し込み条件に「設立2年以上」や「決算書2期分の提出」といった項目が明記されているのが現実です。これでは、どんなに優れた事業計画や熱意があっても、与信審査の土俵にすら上がれないのが実情かもしれません。
これは、あなたの会社に問題があるのではなく、既存の審査システムと、創業期というあなたの会社の状況が、構造的にミスマッチを起こしているだけなのです。



まぁ、正直なところ、私も「事業計画はしっかりしてるんだから大丈夫だろう」と高を括って、メインバンクとネット系の法人カードに申し込んだんです。結果はどちらも否決。社会から『お前はまだ信用できない』と烙印を押されたような、あの無力感は今でも忘れられません。
なぜ協同組合カードが「最適解」なのか?
では、どうすればいいのか。答えはシンプルで、協同組合のカードという「別のルート」を選ぶことです。
このカードはクレジットカードではないため、カード会社が求める「過去の実績」による審査が存在しません。つまり、設立して1日目であろうと、決算書がまだなかろうと、申し込みが可能なのでです。
創業期に最も重要な経営資源は、経営コンサルタントがよく口にするように「時間」と「経営者の集中力」です。顧客訪問や納品で高速道路を使うたびに、現金で支払って領収書をもらい、それを後で精算する…この一連の作業は、年間で計算すると、決して無視できないほどの時間と手間を奪っていきます。
審査に時間を取られてやきもきしたり、煩雑な経費精算に気を取られたりするよりも、すぐに手に入るカードを確保して、本業に100%集中できる環境を整えること。
これこそが、事業を一日でも早く軌道に乗せるための、最も賢明な経営判断だと私は考えています。
【個人事業主向け】個人事業主ETCカードは手軽さ重視で選ぶ
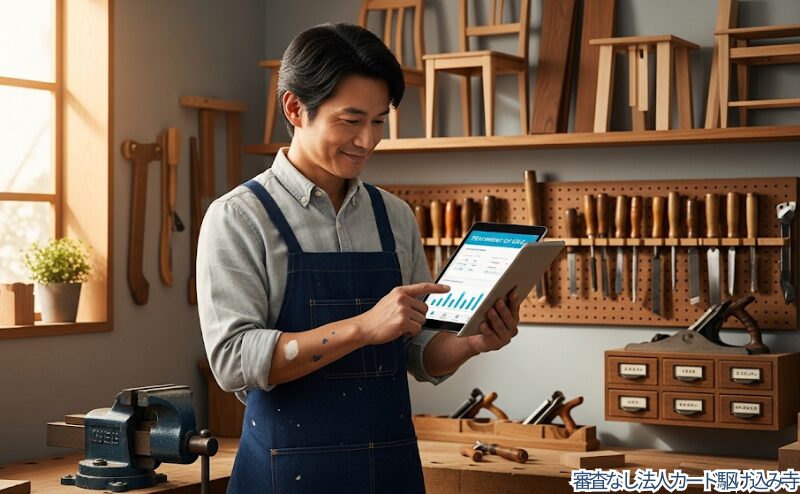
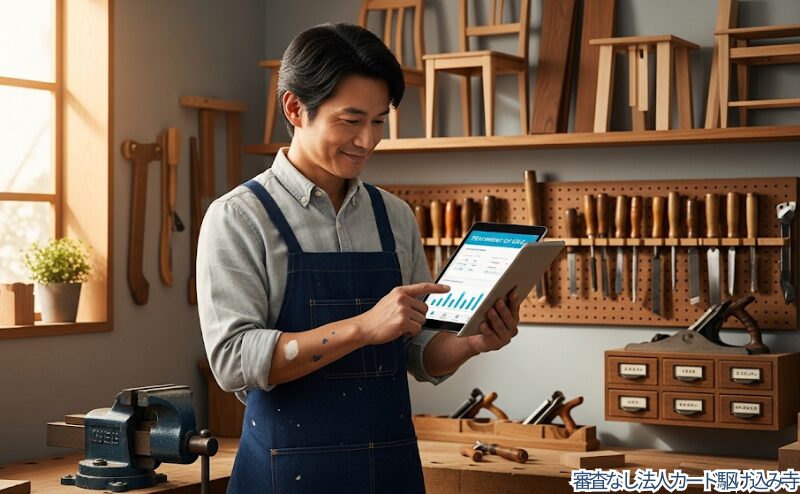
個人事業主の方、特に現場仕事に情熱を注ぐ職人気質の方にとって、審査の壁以上に切実なのが「経費管理の面倒さ」ではないでしょうか。私にも経験がありますが、事業とプライベートの支出をきっちり分けたい、というニーズは本当に大きいものだと感じます。
毎年やってくる「確定申告」という名の悪夢
もちろん、個人用のクレジットカードに付帯したETCカードを事業で使うことも可能です。しかし、確定申告の時期になって、一年分の利用明細の中から事業で使った高速代だけを蛍光ペンで拾い出す、あの気の遠くなるような作業を想像してみてください…。考えただけで、少しウンザリしますよね。
ある調査では、個人事業主が経費精算に費やす時間は、年間で平均50時間にも及ぶというデータもあるくらいです。これは、丸々一週間以上、本来の仕事や家族との時間を、面倒な事務作業に奪われている計算になります。



私の税理士がよく言うんですよ。「○○さん、税務調査官が最初にどこを見るか知ってますか?通帳やカード明細の公私混同ですよ」って。
ここが曖昧だと、『この人の経費は全体的に信用できないな』という心証を与えかねない。そうなると、他の経費まで厳しく見られるリスクがある。だから、口を酸っぱくして「分けてください」って言うのは、結局、あなたを守るためなんです。
面倒からの解放こそが、最大の価値
ここで、協同組合が発行するETCカードが、面倒を嫌う方にとって、非常に頼もしい選択肢となります。このカードは、個人事業主でも屋号で申し込むことができ、クレジット審査もありません。これにより、「事業専用のETCカードを持つ」という、経理上の理想的な状態をいとも簡単に実現できるのです。
このカードがもたらす、たった一つの、しかし絶大なメリット
それは、毎月(または毎年)送られてくる利用明細書が、そのまま事業で使った高速道路代の経費証明になる、ということです。つまり、確定申告の際には、この明細をそのまま税理士さんに渡すだけでOK。これ以上ないほどシンプルだと思いませんか?
プライベートの支出と混ざる心配がなく、経費管理に頭を悩ませる時間から解放される。この「手軽さ」と「精神的な安心感」こそが、日々現場で汗を流すあなたにとって、何よりの価値ではないでしょうか。あなたの時間は、もっと価値のある、あなたの専門技術のために使われるべきなのですから。
経理担当者向けは信頼性と管理のしやすさ


次に、すでに事業が軌道に乗っており、従業員のために複数のETCカードを安定的に手配したい、という経理・総務担当者の視点で考えてみましょう。会社の屋台骨を支える方々にとって、最優先すべきは「事業インフラの安定確保」と「管理業務の徹底的な効率化」、この2点に集約されるでしょう。
潜むリスク:クレジットカード会社の「途上与信」
ご存知の通り、クレジットカード会社の法人カードは、会社の業績が悪化すると、新規発行を停止されたり、利用可能枠を減らされたりするリスクが常に伴います。
カード会社は「途上与信」といって、信用調査会社(帝国データバンクなど)の評点などを基に、定期的に取引先の信用力をチェックしています。国税庁の統計によれば日本企業の約6割が赤字決算というデータもある中で、自社の業績が一時的に落ち込んだだけで、事業に必要なインフラが脅かされる可能性があるのです。
これでは、事業計画に沿った車両の増車もおぼつかなくなってしまいます。企業のBCP(事業継続計画)という観点からも、特定の金融機関だけに決済インフラを依存するのは、賢明とは言えないかもしれません。
解決策:協同組合カードがもたらす2つの戦略的メリット
一方、協同組合の法人ETCカードであれば、前述の通り、会社の財務状況は問われません。これを、経理・総務担当者の視点から見ると、2つの大きな戦略的メリットがあると言えます。
メリット1:事業継続性を高める「安定供給力」
協同組合のカードは、会社の業績に関わらず、必要な枚数のカードを安定的に発行してもらえます。「来週納車されるトラックのETCカードが、急に発行できなくなった…」といった最悪の事態を未然に防げるのです。これは、会社のインフラを支える担当者にとって、非常に大きな安心材料となるはずです。
メリット2:内部統制を強化する「管理のしやすさ」
多くの組合では、Web上で利用明細をCSV形式でダウンロードできるため、会計ソフトへの取り込みもスムーズです。さらに、カードによっては車両番号と紐づけて管理できるため、どの車両が・いつ・どの区間を利用したかが一目瞭然となります。これにより、不正利用を抑止し、内部統制を強化する効果も期待できるでしょう。経理業務の大幅な効率化に直結する、実務的なメリットも大きいと言えます。



つまり、協同組合のカードを選ぶことは、単に「作れないから仕方なく」という消極的な選択ではありません。会社の財務状況という不確定要素から事業インフラを切り離し、盤石な管理体制を構築するという、経理担当者としての、プロフェッショナルで戦略的な判断なのです。



さて、ここまで読んでいただいたあなたなら、もうお分かりのはずです。
設立直後であろうと、個人事業主であろうと、赤字決算であろうと、今のあなたの状況を打開する最適解は、審査の仕組みそのものが違う「協同組合のETCカード」だということに。
この先で、代表的な2つの組合を徹底的に比較・解説していきますが、「もう待てない、今すぐこの状況を解決したい!」という方のために、先に結論となる2つの選択肢をお見せします。
どちらもあなたの事業の強い味方になることは間違いありません。「コスト」を取るか、「サイトの分かりやすさ」を取るか。ご自身の性格に合う方を選んでみてください。
【コストで選ぶなら】高速情報協同組合
発行手数料・年間手数料が明確に安く、30年近い運営実績を持つ組合です。1円でもコストを抑えたい創業者の方や、会社の経費にシビアな経理担当者の方に、最も合理的な選択肢です。
【手軽さで選ぶなら】ETC協同組合
サイトが分かりやすく、申し込みもスムーズ。「難しいことは考えず、とにかく手軽に1枚作りたい」という個人事業主の方や、直感的な安心感を重視する方にフィットする選択肢です。
ETCパーソナルカードという選択肢もある


ここまで組合のカードを主軸におすすめしてきましたが、公平を期すために、もう一つの選択肢についても触れておかなければなりません。それが、NEXCO各社などが共同で発行している「ETCパーソナルカード(パソカ)」です。こちらもクレジット審査なしで発行できるため、選択肢の一つとして検討される方もいらっしゃるでしょう。
ただ、私個人の意見としては、事業用途で、特にキャッシュフローを重視する創業期の経営者が選ぶには、少し慎重になるべきだと感じています。
最大のハードル:事業のキャッシュフローを圧迫する「デポジット制度」
ETCパーソナルカードが事業用途に向かない最大の理由は、その独特な「デポジット(保証金)制度」にあります。
このカードは、申し込み時に最低でも20,000円のデポジットを預ける必要があります。さらに、このデポジット額は、月間の平均利用額の4倍と定められており、もし高速道路の利用が増えれば、デポジットの増額を求められることもあるのです。
【要注意】デポジットが運転資金をロックする具体例
例えば、営業車3台がそれぞれ月に平均2万円の高速道路を利用するとします。
この場合、1台あたりの必要デポジット額は8万円(2万円×4倍)。3台分となると、合計で24万円もの現金を、ただカードを維持するためだけに預けなければなりません。
言うまでもなく、このデポジットはカードの利用料金の支払いに充当することはできません。そして、解約するまで返還されないため、運転資金として使えるはずだったお金が、長期間ロックされてしまうことになります。



ファイナンスの専門家は、企業の財務健全性を見るときに、PL(損益計算書)の黒字よりも、CF(キャッシュフロー計算書)のプラスを重視します。デポジットのように、資産として計上されても自由に動かせないお金は「死に金」とも呼ばれ、キャッシュフローを悪化させる要因と見なされるのです。
組合カードとの比較で見える、決定的な違い
このデポジット制度は、1社あたり1万円の出資金(脱退時返金)で済む協同組合のカードと比較すると、その差は歴然です。特に、複数の車両でカードを利用したいと考えている事業者にとっては、その負担は計り知れません。
もちろん、年会費1,257円(税込)も別途かかります。ETCパーソナルカードは、クレジットカードを持たない個人の方がETCを利用するための、非常に意義のある制度です。ただ、その制度設計が、法人や個人事業主の「事業用」としての使い方とは、少し相性が良くない、というのが私の見方です。
手元の現金を1円でも多く事業に投資し、成長スピードを加速させたいと考えるなら、より少ない資金拘束で済む協同組合のカードに、圧倒的な優位性があると言えるでしょう。
法人ETCカード審査なしは組合一択!2大組合を徹底比較


この章で解説する内容
- なぜ審査なし?協同組合の仕組みを解説
- 「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」を7項目で比較
- 【料金比較】出資金・手数料など全費用を完全ガイド
- 【最終結論】あなたに合うのはどっち?目的別診断
- 失敗しないために|審査なしカードの注意点
さて、ここからは、法人ETCカードが作れない状況の、いわば「切り札」となる協同組合のカードについて、さらに一歩踏み込んで掘り下げていきます。なぜ審査なしで発行できるのか、そして、具体的にどの組合を選べば後悔がないのか。あなたの疑問を一つひとつ解消していきましょう。
なぜ審査なし?協同組合の仕組みを解説
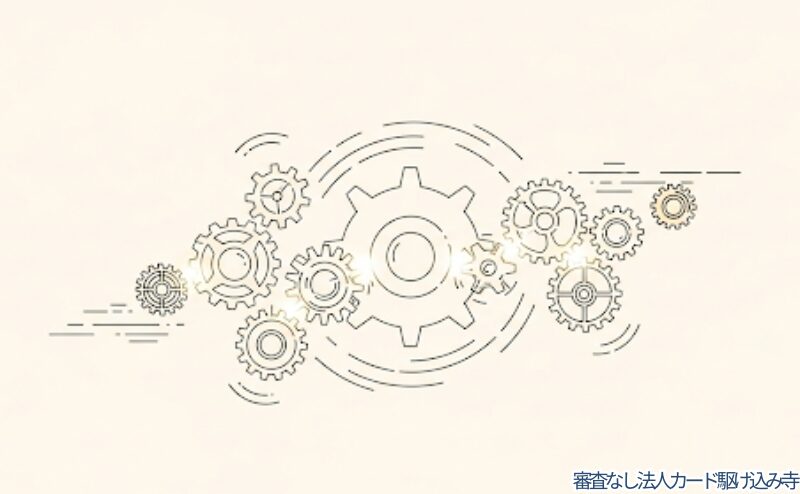
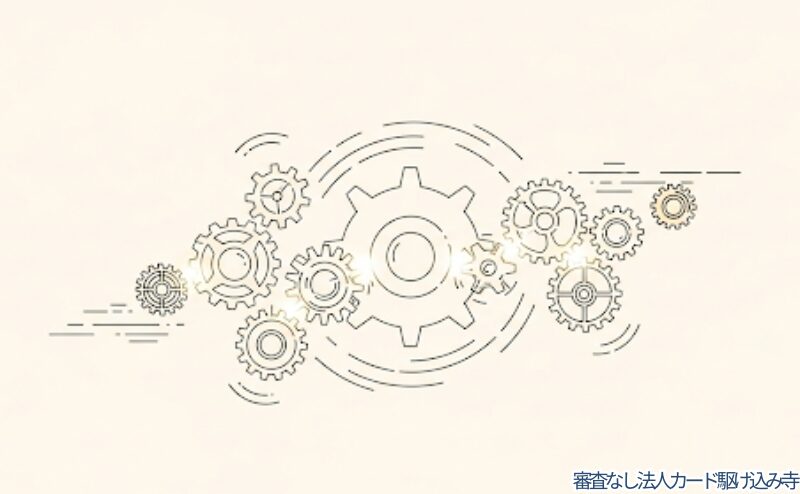
「そもそも、なぜ協同組合のカードは審査がないの?」
ここまで読み進めていただいた方なら、一度はこう思われたのではないでしょうか。特に、何度もクレジットカードの審査に落ちた経験がある方ほど、怪しいサービスなのでは…と勘ぐってしまう気持ちも、痛いほどよく分かります。



まぁ、正直なところ、私も最初は半信半疑でした。「そんなうまい話があるのか?」って。でも、その仕組みを知ったとき、長年の疑問が氷解するようにスッキリしたのを今でも覚えています。
結論から申し上げますと、これは決して怪しい裏ワザなどではなく、私たち中小企業や個人事業主を支えるための、非常に理にかなった仕組みなのです。この章では、その核心部分を分かりやすく解説していきますね。
法的根拠のある「公的な団体」
まず大前提として、ここで言う「協同組合」とは、「中小企業等協同組合法」という法律に基づいて設立・運営されている、れっきとした公的な団体です。身近な例で言えば、JA(農協)や生協(コープ)なども同じ協同組合の仲間です。農家の方や地域の方が組合員となって、共同で購買したり、事業を行ったりしていますよね。それの、中小企業版だとイメージしていただくと、より分かりやすいかもしれません。
このように、国の法律に裏付けられた組織であるという点が、何よりの安心材料と言えるでしょう。
個々の信用を束ねる「相互扶助」の仕組み
では、なぜその公的な団体が「審査なし」でETCカードを発行できるのでしょうか。
金融の専門家から見れば、これは「審査がない」のではなく、「審査の尺度が違う」と表現するのが正確かもしれません。クレジットカード会社が「過去の財務実績」という物差しで個々の信用力を測るのに対し、事業協同組合は「組合への加入と出資金の拠出」という、いわば参加の意思表示そのものを信用と見なしているのです。
ETCカード事業においては、組合が、組合員全体を一つの大きな単位として捉え、いわば「信用保証機関」のような役割を果たしています。具体的には、以下のようなステップで成り立っています。
組合カード発行の3ステップ
- あなた:組合に出資金(通常1万円)を預けて、組合の一員(組合員)になる。
- 組合:あなたを含む組合員から集めた出資金などを元手として、高速道路会社(NEXCOなど)に対して一括で利用料金の支払いを保証する。
- 高速道路会社:組合が保証してくれるなら安心だ、ということで、あなたの会社の設立年月や決算状況といった、個別の信用情報を問わずにETCカードを発行する。
このように、組合が間に入ることで、一つひとつは小さいかもしれない個々の事業者の信用を束ね、大きな信用力に変えているのです。これこそが、古くから中小企業が互いに支え合ってきた「相互扶助」の精神であり、歴史に裏付けられた知恵だと言えます。
補足:出資金は「資産」です
そして最も重要な点ですが、この出資金は経費として消えてしまうものではなく、組合を脱退する際には、原則として全額が手元に返還される「預け金」です。法律的に言っても、会社の「資産」として扱われます。このため、実質的なコスト負担は、後ほど解説する発行手数料や年間手数料といった一部の費用に限られるのです。この点を理解すれば、組合の仕組みに対する不安は、かなり解消されるのではないでしょうか。
「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」を7項目で比較
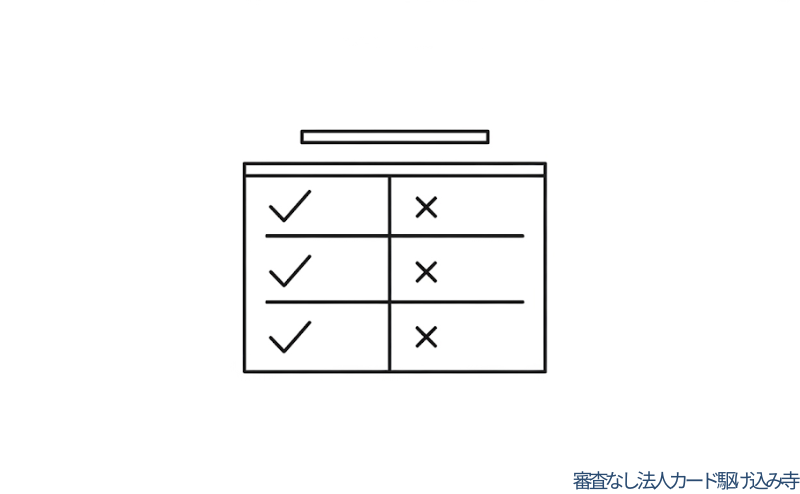
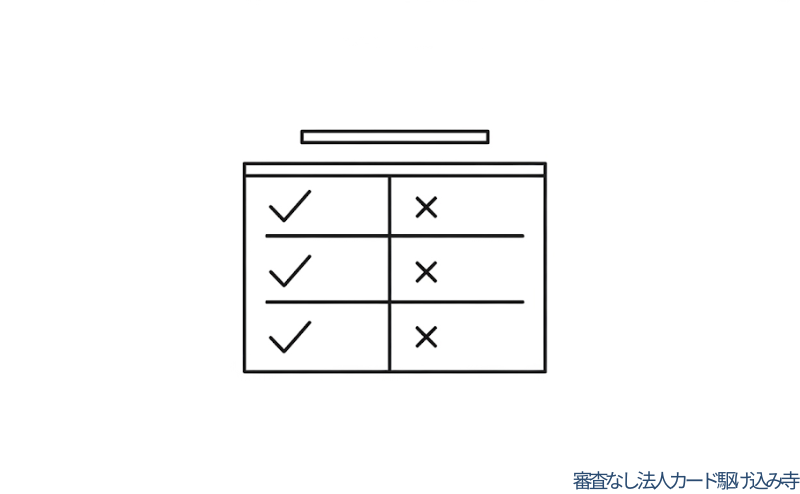
さて、ここからは具体的な組合選びのステップに進んでいきましょう。審査なしの法人ETCカードを発行している組合はいくつか存在しますが、中でも代表的なのが「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」の2つです。
私であれば、まずはこの2つの組合のサービス内容と料金体系を、先入観なく客観的なデータで比較することから始めます。特に、手数料の体系は一見すると分かりにくい部分もあるため、ここでその中身を徹底的に解き明かしていきましょう。
まずは基本情報の比較から
カード選びで特に重要となる8つの項目で、両組合を比較したのが以下の表です。
| 比較項目 | 高速情報協同組合 | ETC協同組合 |
|---|---|---|
| 設立 | 平成5年3月 | 不明 |
| 出資金 | 10,000円/社(脱退時返金) | 10,000円/社(脱退時返金) |
| 発行手数料 | 550円/枚 | 880円/枚 |
| 年間手数料 | 550円/枚 | 880円/枚 |
| 事務手数料 | 走行料金の8% | 走行料金の8% |
| 発行スピード | 最短翌営業日に発送 | 最短翌営業日に発送 |
| カードブランド | UC / セディナ | UC |
| 車両限定 | なし(レンタカー等も利用可) | なし(レンタカー等も利用可) |
※上記の情報は記事執筆にあたり、各組合の公式サイト等から収集したものです。最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。
【最重要】実は横並びの「事務手数料8%」という事実
この比較表を見て、まず何よりも先に注目していただきたい点があります。それは、黄色いマーカーを引いた「事務手数料」の項目です。
注意:本当のコストは利用料金にかかる「事務手数料」
多くの組合系ETCカードでは、カードの発行や維持にかかる固定費とは別に、毎月の高速道路利用額そのものに対して、一定の料率の事務手数料が加算されます。今回比較している2つの組合では、この料率がどちらも「8%」と定められています。
例えば、月に5万円の高速道路を利用した場合、50,000円 × 8% = 4,000円 が、事務手数料として別途請求される、ということです。これは、カードを維持する限り、継続的に発生する最も大きなコストと言えるでしょう。
つまり、一見すると発行手数料や年間手数料に目が行きがちですが、ランニングコストという観点では、両者に大きな差はない、ということが分かります。
では、どこで差がつくのか?
事務手数料が同じである以上、私たちが比較検討すべきポイントは、それ以外の部分になります。



そう考えると、判断基準は意外とシンプルですよね。私がもし今どちらかを選ぶとしたら、以下の2点を重視します。
1. 発行手数料・年間手数料の安さ
これは明確に差が出ています。初期費用となる発行手数料、そして毎年かかる年間手数料は、どちらも高速情報協同組合の方が330円安く設定されています。カードを複数枚発行する場合や、長期間利用することを考えれば、この差は決して無視できません。
2. 運営母体の信頼性・歴史
高速情報協ド組合は、平成5年(1993年)設立という、30年近い歴史を持っています。長年にわたって多くの組合員を支えてきたという事実は、特に会社のインフラを預ける経理担当者の方にとっては、大きな安心材料になるのではないでしょうか。
もちろん、どちらの組合も、私たちのような事業者の駆け込み寺として、非常に価値のあるサービスを提供しています。これらの客観的な事実を踏まえた上で、次の章では、最終的にどちらを選ぶべきか、私の結論を述べたいと思います。
【料金比較】出資金・手数料など全費用を完全ガイド
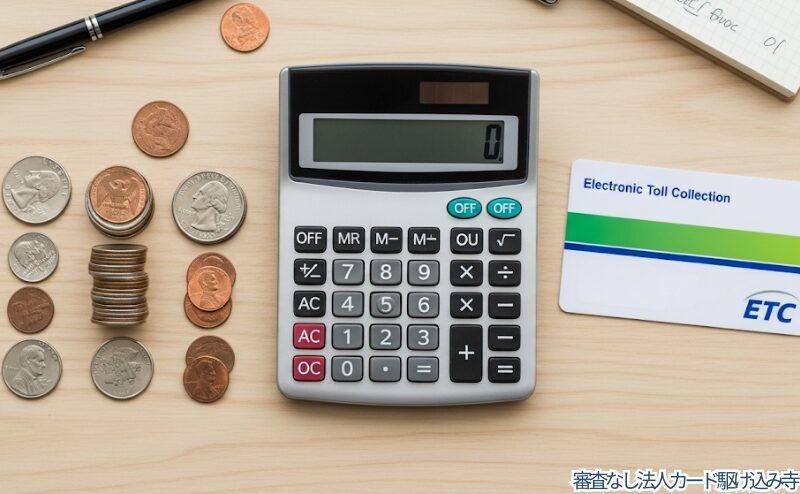
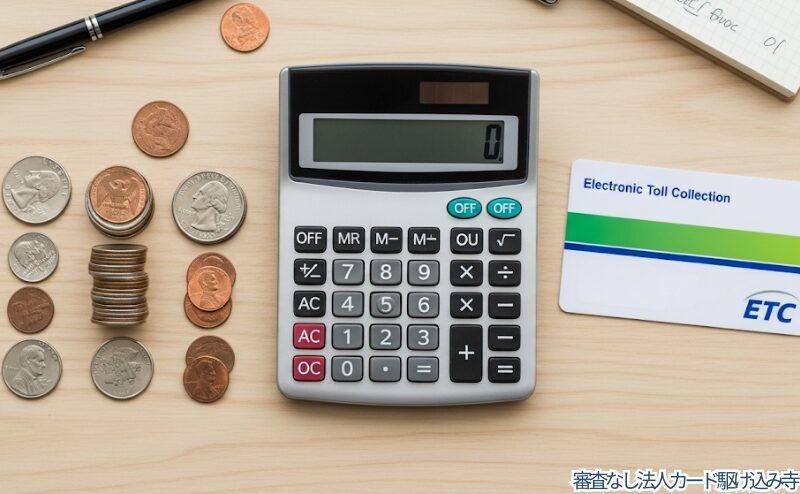
カードを選ぶ上で、やはり費用は最もシビアに比較検討すべきポイントだと思います。しかし、組合のカードの料金体系は少し独特で、表面的な情報だけを見ていると、本当のコストを見誤ってしまう可能性があります。
ここでは、組合のETCカードで必要になる費用を「①出資金」「②固定費」「③変動費」の3つに分類し、その意味合いも含めて、一つひとつ丁寧に整理していきましょう。
費用その1:組合への「出資金」(資産)
まず、組合に加入するために必要なのが「出資金」です。これは、今回比較する2つの組合では、どちらも10,000円/社となっています。
【重要】出資金はコスト(経費)ではありません
この出資金は、組合に預けておく「預け金」であり、経理上は「出資金」という資産科目で計上します。最も重要なのは、組合を脱退する際には全額返還されるという点です。つまり、実質的なコスト(経費)にはなりません。
費用その2:カードの「固定費」(経費)
次に、経費として計上される固定の費用です。これには、カード発行時に一度だけかかる「発行手数料」と、毎年かかる「年間手数料」の2つがあります。ここで、両組合の間に明確な差が出てきます。
- 高速情報協同組合:発行手数料 550円/枚 + 年間手数料 550円/枚 = 合計 1,100円/枚
- ETC協同組合:発行手数料 880円/枚 + 年間手数料 880円/枚 = 合計 1,760円/枚
このように、カード1枚あたりの固定費で比較すると、高速情報協同組合の方が年間で660円安いことが分かります。(※初年度の比較。2年目以降は年間手数料の差で330円となります)
費用その3:最も重要な「変動費」(経費)
そして、ここからが最も重要なポイントです。組合のカードのトータルコストを考える上で、絶対に無視できないのが、毎月の高速道路利用額に応じて発生する「変動費」、つまり「事務手数料」です。
注意:本当のコストは利用料金にかかる「事務手数料」
前章の比較表でも触れましたが、今回比較している2つの組合では、毎月の高速道路利用額に対して、どちらも一律で8%の事務手数料が加算されます。
この事務手数料こそが、年間のトータルコストの大部分を占めることになる、本当のコストの正体なのです。
【シミュレーション】結局、年間コストはいくらになる?
では、これらの固定費と変動費を踏まえて、実際の年間コストはいくらになるのでしょうか。月の高速道路利用額別にシミュレーションしてみました。
| 月の利用額 | 年間事務手数料(8%) | 高速情報協同組合 年間合計コスト | ETC協同組合 年間合計コスト |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 9,600円 | 10,700円 | 11,360円 |
| 30,000円 | 28,800円 | 29,900円 | 30,560円 |
| 50,000円 | 48,000円 | 49,100円 | 49,760円 |
| 100,000円 | 96,000円 | 97,100円 | 97,760円 |
※年間合計コスト = (月の利用額×12ヶ月×8%) + 発行手数料 + 年間手数料 で計算(初年度の場合)
【結論】コストで選ぶなら、答えは一つ
このシミュレーションが示す通り、変動費である事務手数料(8%)が同じであるため、年間のトータルコストの差は、単純に固定費(発行手数料+年間手数料)の差額である660円(初年度)にしかなりません。
つまり、高速道路をどれだけ利用したとしても、コスト面では常に「高速情報協同組合」の方が安くなるという、非常にシンプルな結論が導き出せます。
【最終結論】あなたに合うのはどっち?目的別診断


さて、様々な角度から2つの組合を比較してきました。これまでの分析で、コストの安さと運営実績では「高速情報協同組合」に明確な優位性があることが分かりました。
しかし、カード選びの基準は、必ずしも数字やデータだけではありません。ウェブサイトの分かりやすさや、申し込みのスムーズさといった「感覚的な相性」も、特に時間のない経営者にとっては重要な判断基準になるはずです。
ここでは、あなたが「何を最も重視するか」という視点から、それぞれの組合がどんな方にフィットするのか、私なりの最終結論をまとめてみました。



言ってしまえば、どちらの組合も、ETCカードが作れずに困っている私たち事業者の強い味方であることは間違いありません。その上で、あえて「どちらかを選ぶなら」という視点で、それぞれの魅力を解説しますね。
▼コストと実績を最重視し、最も合理的な選択をしたいあなたへ
→ 迷わず「高速情報協同組合」が最適です。
このような方には、高速情報協同組合をおすすめします。
- 1円でもコストを抑えたい創業者の方
- コストと信頼性を重視する経理担当者の方
推奨する理由は、これまでの分析通り、極めて明快です。
① 明確なコスト優位性:
変動費(事務手数料8%)が横並びの中、発行手数料・年間手数料といった固定費が明確に安いため、トータルコストで常に優位に立ちます。
② 圧倒的な実績と信頼性:
平成5年(1993年)設立という約30年の運営実績は、事業の重要なインフラを安心して任せられる、何よりの証拠と言えるでしょう。
数字と実績という、揺るぎない事実に基づいて、最も堅実で合理的な選択をしたいあなたにとって、これ以上ないパートナーとなるはずです。
高速情報協同組合の公式サイト(セディナ)はこちら
▼手続きの分かりやすさを重視し、直感的に選びたいあなたへ
→ 「ETC協同組合」も有力な選択肢です。
このような方には、ETC協同組合を検討する価値があります。
- とにかく面倒なことが苦手な個人事業主の方
- ウェブサイトの印象や申し込みやすさを重視する方
コスト面では一歩譲るものの、ETC協同組合には以下のような魅力があります。
① ウェブサイトの分かりやすさ:
公式サイトは、初めての方でも迷わず申し込みまで進めるよう、丁寧な案内と配慮が感じられます。「手続きで迷いたくない」という方には安心感があります。
② スムーズな申し込み体験:
わずかなコスト差よりも、申し込みプロセス全体の分かりやすさや、第一印象の安心感を重視したいと考えるなら、有力な選択肢となるでしょう。
「難しいことは考えたくない、とにかくスムーズに1枚作りたい」というニーズに、まっすぐ応えてくれる組合です。
いずれにしても、どちらの組合も、あなたの事業を前に進めるための頼もしいツールであることは間違いありません。ご自身の事業の状況や、あなた自身の性格に合った、後悔のないパートナーを選んでください。
失敗しないために|審査なしカードの注意点


ここまで組合カードのメリットを多くお伝えしてきましたが、物事には必ず光と影があります。良い情報だけを伝えて契約を促すのは、誠実な態度とは言えません。契約してから「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、あなたが本当に知っておくべき注意点やデメリットを、正直にお伝えします。
【最重要】走行料金にかかる「事務手数料8%」
まず、これが最も重要な注意点です。料金比較の章でも触れましたが、組合の法人ETCカードを利用する上で、最大のコストとなるのが「事務手数料」です。
【警告】利用額の8%が手数料として加算されます
今回ご紹介した2つの組合では、毎月の高速道路利用額の合計に対して、一律で8%の事務手数料が上乗せされて請求されます。
例えば、月に50,000円の高速道路を利用した場合、請求額は50,000円 + 事務手数料4,000円(5万円の8%)= 合計 54,000円となります。年間手数料とは別に、この変動費が常にかかるということを、必ず理解しておいてください。これが、審査なしでカードを利用するための、実質的なサービス利用料なのです。
支払いサイクルがキャッシュフローに与える影響
次に、支払いサイクルも確認が必要です。多くの組合では「月末締め、翌々月8日払い」といった、通常のクレジットカードとは異なる支払いサイトが設定されています。
これは、利用月から支払いまでに1ヶ月以上のタイムラグがあることを意味します。一見すると支払いが先延ばしにできて楽に思えるかもしれませんが、キャッシュフロー管理が煩雑になるというデメリットもあります。特に創業期の企業にとっては、資金繰り計画にこのサイクルをしっかり組み込んでおくことが重要です。
法人としてのクレジットヒストリー(クレヒス)が育たない
これは、特に創業したばかりの方に知っておいてほしい、長期的な視点でのデメリットです。
補足:クレジットヒストリー(クレヒス)とは?
法人や個人が、クレジットカードやローンなどを「契約通りに利用・返済した履歴」のことです。良いクレヒスを積み重ねることで、社会的な信用が高まり、将来的に銀行融資や他の法人カードの審査で有利になります。
協同組合のカードは、クレジットカードではないため、いくら利用しても、あなたの会社のクレジットヒストリーは一切育ちません。
設立間もない会社にとって、法人カードをきちんと使い続けることは、会社の信用を育てるための重要な活動の一つです。組合のカードは、あくまで「今を乗り切るための緊急避難的な一手」と割り切り、いずれは自社の信用で法人クレジットカードを作ることを目指す、という視点も忘れないでください。
【朗報】レンタカーでも使える!車両限定はありません
最後に、これはデメリットではなく、むしろ広く知られていない大きなメリットです。
一部で「登録した車両でしか使えない」という情報を見かけることがありますが、今回ご紹介した2つの組合の法人ETCカードは、車両限定がありません。つまり、急な出張で使ったレンタカーや、代車、従業員の私有車など、どの車でも利用することが可能です。この柔軟性の高さは、通常の法人カードにはない、非常に大きな利点と言えるでしょう。
まとめ:法人ETCカード作れない悩みは審査なしの組合で即解決


最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。法人ETCカードが作れずに困っているあなたの、最後のひと押しになれば幸いです。
- 法人ETCカードが作れない悩みは多くの創業者や個人事業主が経験する
- 設立直後や赤字決算ではクレジットカード会社の審査通過は難しい
- 解決策は会社の信用情報が問われない協同組合のETCカード
- 組合のカードは出資金を預けることで審査なしで発行される
- 出資金1万円は脱退時に返還されるため実質的なコストではない
- 創業者にはスピードと実績のある組合カードが最適解となる
- 個人事業主は経費管理が劇的に楽になるという大きなメリットがある
- 経理担当者にとっては会社の状況に左右されない安定供給が魅力
【コストで選ぶなら】高速情報協同組合
発行手数料・年間手数料が明確に安く、30年近い運営実績を持つ組合です。1円でもコストを抑えたい創業者の方や、会社の経費にシビアな経理担当者の方に、最も合理的な選択肢です。
【手軽さで選ぶなら】ETC協同組合
サイトが分かりやすく、申し込みもスムーズ。「難しいことは考えず、とにかく手軽に1枚作りたい」という個人事業主の方や、直感的な安心感を重視する方にフィットする選択肢です。