この記事は約29分で読めます。
ガソリン・ETCカードのインボイス対応|請求書1枚で経理は完結

インボイス制度が始まってからというもの、経費精算の現場、特に高速道路料金の扱いは、本当に混乱を極めていますよね。机の上に積み上げられた、クシャクシャの利用証明書やETCレシートの山…。
「一体いつまで、この証憑集めを続ければいいんだ…」と頭を抱える経理担当者の方。
「この処理で本当に正しいのか?」と、1円のミスも許されない帳簿を前に自問自-答を繰り返す、実直な一人親方の方。
そして、「インボイス対応が重要」と聞き、何から手をつければいいか途方に暮れている、多忙な創業者の方。
その気持ち、痛いほどよく分かります。何を隠そう、私自身が、その「出口の見えないトンネル」で迷い、もがき苦しんだ一人なのですから。
 筆者
筆者私も40代でネットショップ事業を立ち上げた個人事業主ですが、制度開始当初は「なんとかなるだろう」と、正直なところ高をくくっていました。しかし、最初の月締め作業でその考えが甘かったことを痛感させられます。山積みの書類を前に、「この請求書はインボイスの要件を満たしているか?」「そもそも、このやり方で会社と従業員を守れるのか?」と、自身の見通しの甘さを呪った夜は一度や二度ではありません。
この記事は、そんな過去の私と同じ轍を踏んでほしくない、という切実な想いで書いています。
その場しのぎの「対症療法」としての証憑集めに、あなたの大切な時間と気力をこれ以上すり減らすのは、もう終わりにしましょう。この記事では、「請求書1枚」ですべてが完結する、本質的な「根本治療」の方法を、誰にでも分かるように、そして具体的に提示することをお約束します。もう、あなたは一人で悩む必要はありません。
- なぜ従来のカード明細ではインボイス要件を満たせないのかが、ハッキリと分かります。
- 面倒な「利用証明書」集めから解放される、具体的な解決策を知ることができます。
- あなたの会社の状況に合わせた、最適な法人ETCカードの選び方が明確になります。
- 煩雑な経理作業から解放され、より本質的な業務に集中できる未来が見えてきます。
もう限界!「クレジットカードなし」の法人ETCカードが必要な理由
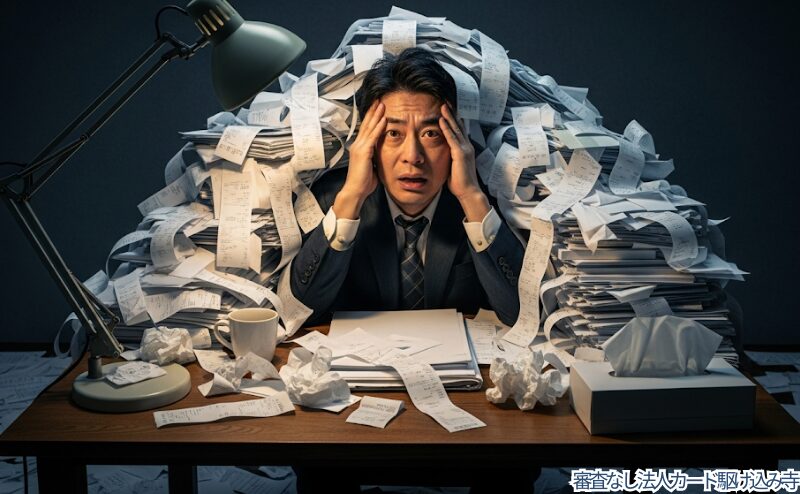
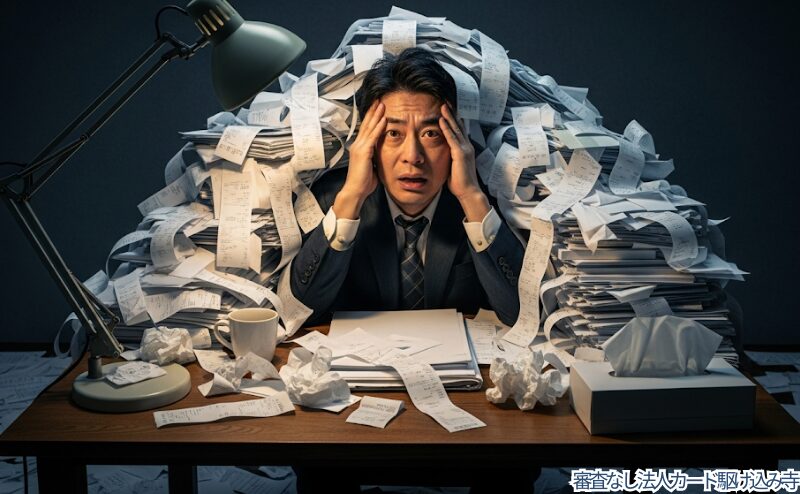
さて、本題に入る前に、まずは現状の課題をしっかり共有しておきたいと思います。なぜ、私たちはここまで追い詰められてしまったのか。その原因を理解することが、解決への第一歩になりますから。
なぜ?カード会社の利用明細書はインボイスにならない


インボイス制度が始まってからというもの、「今まで通り、クレジットカードの利用明細書があれば大丈夫だろう」と考えていた方は、きっと少なくないはずです。ええ、何を隠そう、かつての私もそうでした。制度の概要は頭に入っていたつもりでも、「長年慣れ親しんだこのやり方が、根底から覆ることはないだろう」と、どこか楽観視していたんです。しかし、これは致命的な勘違いでした。
特に、顧問先の経理担当者から「先生、このカード明細で仕入税額控除できますよね?」と無邪気に尋ねられ、「ええ、もちろんですよ」と安請け合いしてしまった日のことは、今でも冷や汗と共に思い出します。後日、「申し訳ない、あれでは要件を満たせないんです…」と頭を下げることになった私の情けなさ。長年の慣習と思い込みが、いかにプロとしての判断を鈍らせるか、身をもって痛感した瞬間でした。



あなたも、もしかしたら今、会計ソフトの画面と書類の山を前にして、過去の私と同じように「このやり方で、本当に大丈夫なのか…?」と眉間にしわを寄せているかもしれません。その不安、痛いほどよく分かります。だからこそ、まずは「なぜダメなのか」という根本原因を、一緒に、そして徹底的に解明していきましょう。ここを理解することが、最適な解決策への最短ルートになるのですから。
そもそもインボイスとは? 6つの必須項目を最終確認
まず大前提として、国税庁が「適格請求書(インボイス)」として認めるためには、以下の6つの項目がすべて記載されている必要があります。一つでも欠けていれば、原則として消費税の仕入税額控除は認められません。これは、税務署が「誰が、誰に、いつ、何を、いくらで取引し、消費税をいくら預かったか」を正確に把握するための、絶対的なルールだと考えてください。
【インボイス 6つの必須記載事項】
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号:「T」から始まる13桁の番号。これがなければ始まりません。
- 取引年月日:取引を行った日付です。
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨):「ガソリン代」「高速道路料金」など。※軽減税率対象品目(8%)の場合はその旨も記載が必要です。
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率:10%対象と8%対象の合計金額と、それぞれの税率。
- 税率ごとに区分した消費税額等:税率ごとに分けた、具体的な消費税額。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称:あなたの会社名や屋号です。
このリストを念頭に、お手元のクレジットカードの利用明細書を見てみてください。もうお分かりですよね。一般的な利用明細書には、「1. 発行事業者の登録番号」や「5. 税率ごとの消費税額」、場合によっては「6. あなたの会社名」すら記載されていないケースがほとんどです。これが、従来のやり方が通用しなくなった、直接的な理由です。
【本質】なぜ記載がない? カード会社とサービス提供者の「役割の違い」
では、もう少し深掘りしてみましょう。「なぜ、これほど重要な情報をカード会社は記載してくれないのか?」と、疑問に思うかもしれません。これはカード会社の怠慢ではなく、消費税法における「役割」の違いに起因する、構造的な問題なのです。
結論から言うと、クレジットカード会社は「決済を代行する者」であって、「サービスや商品を提供した当事者」ではないからです。
インボイスを発行できるのは、あくまであなたに高速道路の通行サービスを提供した「NEXCOなどの高速道路会社」や、ガソリンを販売した「ガソリンスタンド」だけです。クレジットカード会社は、あなたが彼らに支払うべき代金を一時的に立て替え、後でまとめて請求しているに過ぎません。つまり、カード会社とあなたの間には、サービスの提供という「取引の事実」が存在しないのです。
【専門家の視点】取引の当事者は誰か?
税務の世界では、「取引の当事者」が誰であるかを非常に重視します。ETCやガソリン代の場合、「サービス提供者(高速道路会社、SS)⇔利用者(あなた)」という関係が本来の取引です。カード会社は、この取引の外側で金銭の仲介をしているに過ぎません。そのため、取引の当事者ではないカード会社が、その取引内容を証明するインボイスを発行することは、そもそも制度上できない、というわけです。
この関係性を、以下の表で整理すると、より明確に理解できるかと思います。
| 役割 | 主体 | 発行できる書類 |
|---|---|---|
| サービスの提供者 (例:高速道路会社、ガソリンスタンド) | 取引の直接の当事者 | 適格請求書(インボイス) |
| 決済の代行者 (例:クレジットカード会社) | 金銭の仲介者に過ぎない | 利用代金明細書(インボイスではない) |
このように考えると、クレジットカードの利用明細書がインボイスとして認められないのは、至極当然のことだと言えます。そして、この構造的な問題を理解することこそが、なぜ私たちが「利用証明書集め」という不毛な作業から抜け出し、「請求書1枚で完結する」という根本的な解決策へシフトしなければならないのか、その必要性をはっきりと示しているのです。
地獄の経費精算。ETC利用証明書と領収書の山
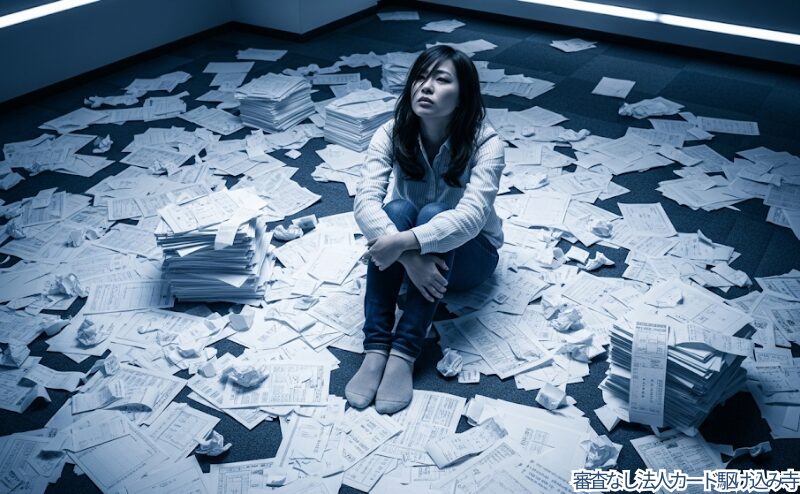
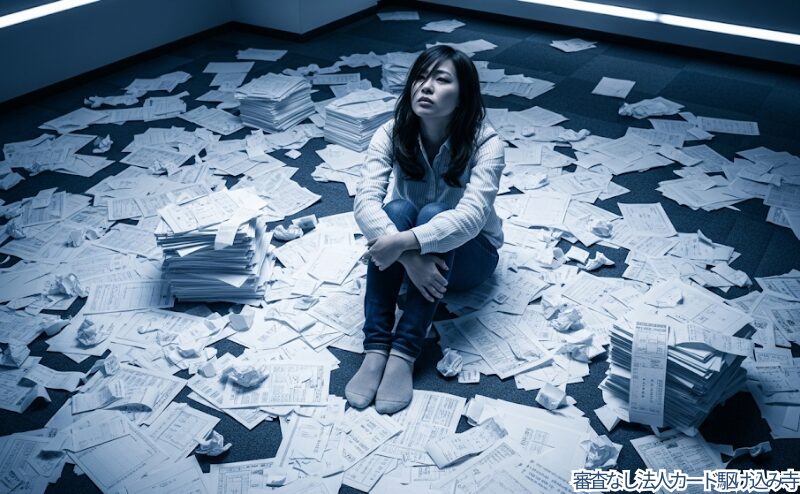
クレジットカードの利用明細書がインボイスとして認められない。この厳しい現実を前に、国が代替案として示したのが、「ETC利用照会サービス」から利用履歴ごとに「利用証明書」をダウンロード・保存するという方法でした。一見、確実な解決策に思えるかもしれません。しかし、これが実務の現場に、新たな、そしてより深刻な問題を引き起こすことになったのです。
特に、複数の従業員が日常的に高速道路を利用する会社や、正確な経費管理を徹底したい個人事業主の方にとって、この方法はあまりにも非効率で、リスクを伴うものでした。言ってしまえば、一つの問題を解決するために、さらに厄介な問題をいくつも抱え込むようなものだったのです。
第一の壁:利用履歴の「一件ずつの」手動ダウンロード
まず立ちはだかるのが、利用証明書の取得方法そのものの煩雑さです。「ETC利用照会サービス」は、そもそも法人全体の経費管理ツールとして設計されていません。そのため、経理担当者が全従業員の利用分を一括でダウンロードする、といった便利な機能は存在しないのです。
つまり、従業員一人ひとりが自分の走行履歴を一件ずつ表示させ、それをPDFで保存するか、印刷して提出する、という作業が必須になります。これが、全ての非効率の始まりでした。
第二の壁:現場で起こる「証憑回収」という名の消耗戦
この「一件ずつの手作業」は、必然的に現場の混乱を招きます。



少し想像してみてください。営業担当者が15名いる会社で、それぞれが月に平均10回、高速道路を利用するとします。すると、月末の経理部には、単純計算で150枚もの利用証明書が集まる(あるいは、集まらなければならない)わけです。もちろん、これは理想論。実際には「提出を忘れていました」「データをどこに保存したか分からなくなりました」という報告が相次ぎ、経理担当者は督促と確認に追われることになります。
悪気がないのは分かっているんです。営業担当者は日々の目標に追われていますから。その中で、数十円、数百円の領収書一枚一枚を完璧に管理しろ、というのは、現実的には酷な話かもしれません。ですが、経理の立場からすれば、証憑がなければ仕入税額控除は認められない。この板挟みが、担当者の心身をすり減らしていくのです。
私がこれまで見てきた多くの現場では、月末になると経理担当者のデスクは、しわくちゃの利用証明書や、印字が消えかかった感熱紙のレシートの山で埋め尽くされていました。「この登録番号、8なのかBなのか判別できない!」「そもそも、このレシートはインボイスの要件を満たしていないじゃない!」そんな悲鳴にも似た声が聞こえてくる光景は、決して珍しいものではありませんでした。
【計算例】証憑回収に潜む「見えないコスト」の正体
この非効率な作業は、目に見えないコストとなって経営を圧迫します。例えば、先ほどの150枚の証憑を処理するケースで考えてみましょう。
- 従業員への提出依頼、回収、内容の確認、会計ソフトへの入力、ファイリング…1枚あたりにかかる時間を、控えめに見積もって5分とします。
- 月間の総作業時間:150枚 × 5分 = 750分 = 12.5時間
- 経理担当者の時給を2,500円と仮定した場合、この作業だけで毎月31,250円、年間で375,000円もの人件費が、この単純作業のためだけに消えている計算になるのです。
【専門家の視点】単なる非効率では済まされない「税務リスク」
そして、この問題は「非効率」や「コスト」という言葉だけでは片付けられません。より深刻なのは、会社全体を揺るがしかねない「税務リスク」に直結している点です。
手作業の証憑管理が引き起こす3つの経営リスク
- 仕入税額控除の否認リスク:最も直接的なリスクです。たった一枚の証憑の紛失や不備が、納めるべき消費税額の増加に直結します。これが積み重なれば、年間のキャッシュフローに与える影響は決して無視できません。
- 管理体制への信頼失墜リスク:もし税務調査が入った場合、証憑の管理が杜撰であることは、経理全体の管理体制に対する不信感につながります。「この会社は、他の経理処理もずさんなのではないか?」と疑われ、より広範で詳細な調査に発展する可能性も否定できないのです。
- 内部不正の温床となるリスク:現金での立て替え精算や、管理の行き届かない証憑のやり取りは、残念ながらカラ出張や経費の水増し請求といった内部不正の温床となりやすい側面も持っています。
このように、利用証明書を一枚一枚集めるというやり方は、時間とコストを浪費するだけでなく、企業のコンプライアンス体制そのものを危うくする可能性を秘めています。このやり方を続けていては、いずれ限界が来るのは明白です。だからこそ、私たちはこの対症療法的なアプローチから脱却し、問題の根本を断ち切るための次の一手を打たなければならないのです。
ご安心ください。その悩み、解決できます。
この「証憑集めの地獄」から抜け出す方法は、実は驚くほどシンプルです。
あなたの課題に合わせて、根本的な解決策をご確認ください。
ETC利用証明書を
集めるのが限界な方へ
ガソリン領収書の
管理に疲れた方へ
なぜ、これらのカードが根本的な解決策になるのか?その理由を、次の章で詳しく解説していきます。
最適な法人ETCカード(クレジットカードなし)はこれ!選び方完全ガイド


- 【結論】「請求書」1枚でインボイス対応は完結する
- なぜ審査なし?高速情報協同組合カードの仕組み
- あなたに合うのはどっち?組合 vs コーポレートカード
- 組合カード発行!申し込みから利用開始までの流れ
- 【実務】インボイス導入後の勘定科目と注意点
- 【Q&A】経理担当者のよくある質問
- 未来へ!ペーパーレスで戦略的な経理部になるために
前章でお話ししたような、出口の見えない「利用証明書集め」の無限ループ。ですが、安心してください。この問題には、驚くほどシンプルで、かつ効果的な解決策が存在します。ここからは、あなたをその煩わしさから完全に解放するための、具体的な方法についてお話ししていきます。
【結論】「請求書」1枚でインボイス対応は完結する


さて、ここからが本題です。これまでの章で解説してきた、出口の見えない「利用証明書集め」の無限ループ。私自身、散々悩み、探し回り、そしてたどり着いた結論。それは、驚くほどシンプルでした。
もう、答えは一つしかありません。それは、「発行される請求書そのものが、インボイスの要件を完全に満たしている法人ETCカードを選ぶ」ということです。
これ以外の方法では、根本的な解決には至らない。そう断言できます。
もう証憑集めは不要!「一枚の請求書」がすべてを解決する
これがどういうことか、具体的に説明しましょう。この仕組みを導入すれば、従業員が個別に「ETC利用照会サービス」にログインしたり、サービスエリアでわざわざ利用証明書を発行したり、ましてやクシャクシャの領収書を提出したりする必要は、一切なくなります。
あなたの会社に毎月届く、あるいはウェブサイトからダウンロードする「月締めの請求書」たった1枚。そこに、インボイスとして必要な全ての情報が、あらかじめ完璧に記載されているのです。経理担当者は、その請求書1枚を、電子帳簿保存法の要件に従って保存するだけ。たったそれだけで、全従業員の高速道路利用料金に関する仕入税額控除の要件を、完全に満たすことができるのです。
百聞は一見に如かず、です。理想的な請求書がどのようなものか、ご覧ください。
【理想のインボイス対応請求書のイメージ】
一枚の請求書に、カードごとの利用明細と、インボイス要件を満たす情報が集約されています。
| 利用日 | 利用者/カード番号 | 利用区間 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 2025/07/05 | 田中 太郎/CARD-001 | 東京IC → 名古屋IC | 7,300円 |
| 2025/07/10 | 鈴木 次郎/CARD-002 | 首都高 霞が関 → 渋谷 | 300円 |
| 2025/07/12 | 田中 太郎/CARD-001 | 名古屋IC → 京都東IC | 3,500円 |
| (以下、全従業員の利用明細が続く) | |||
| 合計金額 | 〇〇,〇〇〇円 | ||
| 発行事業者:〇〇協同組合 登録番号:T1234567890123 10%対象合計金額:〇〇,〇〇〇円 (うち消費税額等:〇,〇〇〇円) | |||
この請求書一枚で、前述したインボイスの6つの要件がすべて満たされていることがお分かりいただけるかと思います。これこそが、私たちが目指すべき経費精算の姿です。



この解決策に初めてたどり着いた時の感覚は、今でも忘れられません。まるで暗いトンネルの先に、ようやく力強い光が差し込んできたようでした。「あれだけ苦労していた書類の山と、毎月のイライラは一体何だったんだ…」と、正直、呆然としたほどです。この方法を知ってからは、自信を持って顧問先の企業すべてにこの方式への切り替えを提案しています。今では、どの会社の経理担当者からも「月末の風景がまるで変わりました」「本来やるべき分析業務に集中できます」と、感謝の言葉をいただくことが、何よりのやりがいです。
なぜ審査なし?高速情報協同組合カードの仕組み
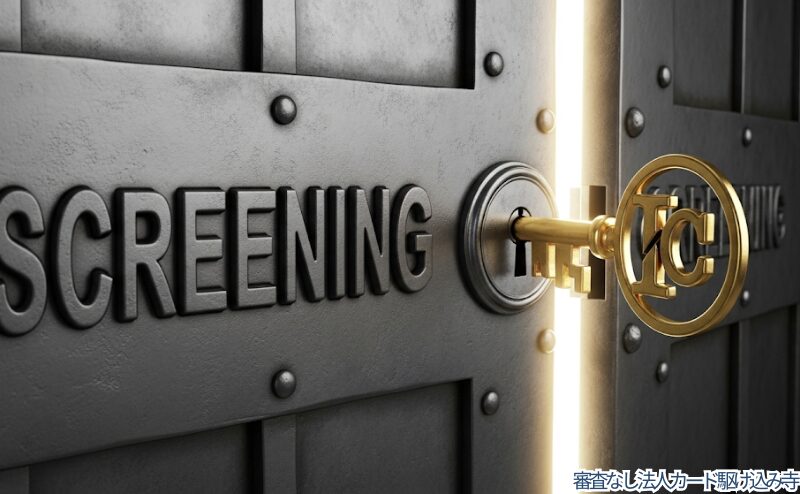
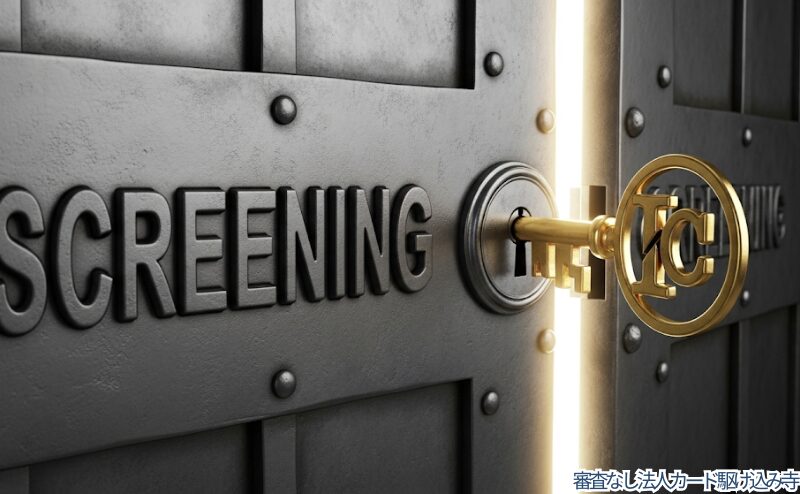
「請求書がインボイスになるのは魅力的だけど、どうせ設立間もない会社や個人事業主は、審査が厳しくて作れないんでしょう?」
ここまで読んで、きっと多くの方がそう思われたはずです。ええ、その懸念はごもっともです。事実、信販会社が発行する一般的な法人クレジットカードは、過去の事業実績や決算書の内容といった「与信情報」を厳格に評価するため、設立から日の浅い事業者にとっては非常にハードルが高いのが現実です。
しかし、ここでご紹介している「高速情報協同組合」などが発行する法人ETCカードは、その前提が根本から異なります。なぜなら、これらのカードは信販会社のクレジットカードではなく、事業協同組合が提供するサービスだからです。
信販会社の「与信審査」が不要になる、独自の仕組み
では、なぜ組合が発行するカードは、信販会社のような厳しい与信審査が不要なのでしょうか。私も最初は、その仕組みを完全に理解するまで半信半疑でした。しかし、その理由は非常に合理的で、中小企業が互いに支え合う「組合」という仕組みの本質に根差したものでした。
そもそも「事業協同組合」とは?
事業協同組合とは、「中小企業等協同組合法」に基づいて設立される法人です。個々の中小企業や個人事業主では実現が難しいことを、組合員が共同で行うことでスケールメリットを生み出し、経営を支援することを目的としています。今回ご紹介する高速情報協同組合やETC協同組合も、経済産業省などから認可を受けた公的な団体であり、その活動の一環として法人向けのETCカードやガソリンカードの発行事業を行っています。
その鍵を握るのが、「出資金(保証金)」という、組合独自の制度です。
これは、カードを申し込む際に、組合に対して1万円の出資金を預けるというもの(この出資金は、組合を脱退する際に全額返金されます)。この仕組みを、賃貸物件を借りる際の「敷金」に例えると、非常に分かりやすいかもしれません。
つまり、この1万円の出資金が担保として機能することで、万が一、ある組合員の利用料金の支払いが滞ったとしても、組合が高速道路会社への支払いを保証できるのです。個々の企業の信用力に頼るのではなく、組合員全員の出資金によって形成される「組合全体の信用力」で、リスクをカバーする。これが、組合カードの核心です。
【カード発行におけるリスク構造の違い】
この違いを理解することが、組合カードの本質を掴む鍵となります。
| 一般的な法人クレジットカード | 組合発行の法人ETCカード | |
|---|---|---|
| リスクの所在 | カード会社(信販会社)が100%のリスクを負う。 | 組合と利用者がリスクを分担する(出資金がリスクを相殺)。 |
| 審査の根拠 | 過去の実績。(財務状況、事業継続年数など) | 未来への保証。(1万円の出資金の有無) |
| 発行のハードル | 新設法人や個人事業主には高い。 | 新設法人や個人事業主でも低い。 |



お分かりいただけたでしょうか。組合のカードは、決して「審査が甘い」わけでも、「誰でも無条件に作れる」わけでもありません。信販会社が行う「過去の実績に基づく与信審査」の代わりに、「出資金という未来への保証」という、まったく別のロジックで信用の問題をクリアしているのです。だからこそ、設立1年目のスタートアップ企業でも、赤字決算の会社でも、そしてかつての私のような個人事業主でも、事業に必要なETCカードを堂々と手に入れることができる。これは、中小企業のために作られた、非常によくできた仕組みだと私は考えています。
あなたに合うのはどっち?組合 vs コーポレートカード


さて、「請求書1枚でインボイス対応が完結する」という理想的なETCカードには、大きく分けて2つの選択肢が存在します。一つは、これまでお話ししてきた「高速情報協同組合」などが発行する組合カード。そしてもう一つが、NEXCOが直接発行する「ETCコーポレートカード」です。
どちらもインボイス対応の請求書が発行される点では同じですが、その特性は全く異なります。あなたの会社の事業規模や、高速道路の「利用スタイル」によって、その損得は大きく変わってきます。ここで両者を徹底的に比較し、あなたにとっての最適解を見極めていきましょう。
2つのカードを6つの軸で徹底比較
まずは、両者の特徴を一覧表で客観的に比較します。特に「割引制度」と「車両限定の有無」が、選択における重要な分岐点となります。
| 比較項目 | 高速情報協同組合カード | ETCコーポレートカード |
|---|---|---|
| 審査 | 原則なし(1万円の出資金で保証) | あり(事業規模、財務状況、NEXCOの基準に基づく) |
| 初期費用 | 出資金1万円(脱退時返金)+ カード発行手数料等 | 保証金(月の利用額の4倍、最低10万円~) |
| 割引制度 | ETCマイレージサービス(利用額に応じたポイント還元) | 大口・多頻度割引(最大40%) ※車両単位で月5,000円超から適用 |
| 車両限定 | なし(レンタカーや従業員の車でも利用可) | あり(事前に登録した車両のみ利用可) |
| 事務手数料 | 組合により異なる(走行料金に対し5%~8%程度) | なし |
| おすすめの対象 | 個人事業主、中小企業、設立間もない会社、レンタカー等の利用が多い会社 | 運送業など、特定の車両で毎月3万円以上をコンスタントに利用する大企業 |
【重要】判断基準はただ一つ「利用スタイル」です
この比較表から見えてくるのは、どちらのカードが優れているか、という単純な話ではないということです。判断基準はただ一つ、あなたの会社の「高速道路の利用スタイル」に尽きます。
こんなあなたには「組合カード」が最適解です
以下に一つでも当てはまるなら、迷わず組合カードを選ぶべきです。
- 創業したばかりで、信販会社の審査に通るか不安だ
- 事業を始めたばかりの個人事業主である
- 初期費用は、できる限り抑えたい
- 高速道路の利用は、月によって変動が大きい
- 営業担当者など、複数の従業員が利用する
- レンタカーやカーシェア、従業員の自家用車を業務で利用する機会がある
- とにかく手続きの煩雑さをなくし、柔軟な運用を最優先したい
こんなあなたは「ETCコーポレートカード」も検討の価値あり
もし、以下の条件をすべて満たすのであれば、ETCコーポレートカードの割引メリットを享受できる可能性があります。
- 設立から数年が経過し、経営が安定している
- 長距離トラックや定期配送車など、特定の車両を保有している
- その特定の車両1台あたり、毎月コンスタントに3万円以上の高速道路利用がある
- 最低10万円以上の保証金を預ける資金的余裕がある
- 車両の登録・変更といった管理業務の手間を許容できる
【専門家の視点】大口割引の裏にある「柔軟性の欠如」というコスト
ETCコーポレートカードの割引率は、確かに魅力的です。しかし、そのメリットは「登録された特定の車両」でしか享受できません。例えば、登録済みのトラックが急な故障で修理に入り、代車としてレンタカーを使った場合、その走行分は割引の対象外。インボイスも別途取得する必要があり、経理の手間が復活してしまいます。この「運用の硬直性」という見えないコストを許容できるかどうかが、導入の大きな分かれ目になるでしょう。



私からのアドバイスを正直に申し上げるなら、この記事を読んでくださっている95%以上の中小企業や個人事業主の方にとっては、高速情報協同組合のカードが最も現実的で、かつ賢明な選択になるはずです。ETCコーポレートカードの割引は、あくまで一部のヘビーユーザー向けの制度です。目先の割引率に惑わされることなく、自社の状況に合った、本当に価値のある一枚を選んでください。経理担当者の手間をなくし、事業全体の生産性を高めるという本来の目的を考えれば、答えは自ずと見えてくるのではないでしょうか。
もう、迷う必要はありません。
あなたの会社の経費精算を劇的に変える「一手」が、ここにあります。
お悩みに合わせて、最適な解決策をお選びください。
ETCの利用証明書集めを
終わりにしたい方
法人ガソリン代の経費を
削減・管理したい方
※もちろん、両方のカードを申し込むことも可能です。
(参考)ETCカード導入に関する詳細記事はこちら
(参考)ガソリンカード導入に関する詳細記事はこちら
組合カード発行!申し込みから利用開始までの流れ


「組合カードのメリットはよく分かった。でも、手続きが面倒なんじゃないか…?」そんな風に、最後の最後で二の足を踏んでしまう気持ち、私も経験者としてよく分かります。新しいことを始める時の、あの何とも言えない億劫さ。ありますよね。
ですが、安心してください。結論から言うと、この組合カードの申し込みプロセスは、驚くほど簡単で、拍子抜けするくらいスピーディーでした。一般的な法人クレジットカードの申し込みに比べれば、その手間は10分の1程度だと言っても過言ではありません。ここでは、あなたが今すぐ行動に移せるよう、発行までの全ステップと、それぞれの「期間の目安」を私の実体験を交えて具体的に解説します。
発行までの全4ステップと「期間の目安」を徹底解説
全体の流れは、Webでの申し込みからカード到着まで、わずか4ステップ。不備なく進めば、申し込みからおよそ10営業日~2週間ほどで、あなたの手元にカードが届きます。
▼カード発行までの流れ▼
STEP 1:Web申込み
↓
STEP 2:書類の準備・返送
↓
STEP 3:出資金の振込み
↓
STEP 4:カード到着!
STEP 1:公式サイトからWeb申込み(所要時間:約5分)
まずは、高速情報協同組合の公式サイトにアクセスし、申し込みフォームに必要事項を入力します。会社の基本情報(社名、住所、代表者名など)を入力するだけなので、パソコンの操作に慣れている方なら5分もかからずに完了するでしょう。最初のハードルは、驚くほど低いのです。
STEP 2:必要書類の準備と返送(期間:書類到着後、数日)
Web申し込みから2~3営業日で、組合から申込書類一式が郵送されてきます。同封の案内に従って、必要事項を記入・捺印し、以下の書類のコピーを添えて返送します。
【準備する書類リスト】
法人の場合:
・履歴事項全部証明書(発行6ヶ月以内のもの)
・代表者の運転免許証など本人確認書類
・ETCカードを実際に利用する車両の車検証
・ETC車載器セットアップ証明書
個人事業主の場合:
・所得税確定申告書
・代表者の運転免許証など本人確認書類
・ETCカードを実際に利用する車両の車検証
・ETC車載器セットアップ証明書
Tip:
創業したばかりでまだ確定申告をしていない個人事業主の方でも、ご安心ください。その場合は、「開業届」の控えのコピーで代用が可能なケースがほとんどです。また、法人の「履歴事項全部証明書」は、法務局のオンライン請求を使えば、役所に出向くことなくPC上で取得できるので時間短縮になりますよ。
STEP 3:出資金1万円の振込み
書類の返送とほぼ同じタイミングで、指定された口座に出資金1万円を振り込みます。これが、与信審査の代わりとなる重要な保証金です。振込手数料は自己負担となりますが、この出資金は組合を脱退する際に全額返金されますので、実質的なコストではありません。
STEP 4:カード到着・利用開始(書類返送から約10営業日~)
あなたが返送した書類と、出資金の振込みが組合側で確認されれば、カードの発行手続きが開始されます。私の場合は、書類をポストに投函してからちょうど2週間後に、待ちに待ったETCカードが会社に届きました。もちろん、カードが届けばその日からすぐに車載器に挿入して利用を開始できます。



いかがでしたでしょうか。「なんだ、これだけか」と思われたのではないでしょうか。私自身、何度も審査に落ちた経験から、法人口座の開設や融資の申し込みのような、煩雑で時間のかかる手続きを想像していました。しかし、実際は拍子抜けするほどスムーズで、「もっと早く知っていれば…」と心から思ったものです。この手軽さとスピード感こそ、日々の業務に追われる私たち中小企業経営者や経理担当者にとって、何よりの魅力だと感じています。
わずか5分のWeb入力で、来月からの経費精算が変わります。
この驚くほどの手軽さを、ぜひご自身で体験してください。
面倒な経費精算とは、今日でサヨナラしましょう。
ETCの経費精算を
自動化したい方はこちら
ガソリン代の管理を
ラクにしたい方はこちら
【実務】インボイス導入後の勘定科目と注意点


さて、ここからは少し専門的な話になりますが、経理の正確性を追求するあなたにとっては、避けては通れない非常に重要なポイントです。無事に新しいカードが届き、インボイス対応の美しい請求書を手に入れた後、それをどのように会計処理すればいいのか。特に、見落としがちな論点について、プロの視点から詳しく解説します。
月々の利用料金の仕訳(勘定科目)
まず、毎月のETC利用料金の会計処理です。これは従来と変わりありません。事業活動における移動のための費用ですので、勘定科目は「旅費交通費」として処理するのが一般的です。インボイス対応の請求書を受け取ったら、以下のように仕訳を行います。
【仕訳例】月のETC利用料金 合計33,000円(うち消費税3,000円)の場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 30,000 | 未払金 | 33,000 |
| 仮払消費税等 | 3,000 |
摘要欄には「〇月分 ETC利用料」などと記載し、証憑として受け取った請求書(インボイス)を紐づけて保存すれば、会計処理は完璧です。
【最重要】見落としがちな「出資金」の会計処理
ここからが、特に注意が必要なポイントです。私が顧問先で見てきた中でも、特に間違いが起こりやすいのが、申し込み時に支払った出資金1万円の扱いです。
注意:出資金は「経費」ではなく「資産」です!
この1万円は、組合に支払う手数料や会費ではありません。あくまで、組合を脱退する際に返還される「預け金」です。したがって、これを支払時に「支払手数料」や「雑費」などの経費として計上するのは、明らかな間違いです。
正しくは、「出資金」や、より丁寧に処理するなら「差入保証金」といった資産の勘定科目で計上します。これは、将来お金が返ってくる「権利」を資産として帳簿に記録しておく、という考え方です。
【出資金支払い時の仕訳例】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 出資金 (または差入保証金) | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
この資産は、将来組合を脱退して出資金が返還された際に、逆の仕訳を行って取り崩すことになります。この処理を間違えると、意図せず利益操作をしたと見なされかねないため、くれぐれもご注意ください。
【上級者向け】意外な盲点「事務手数料」の扱いは?
最後に、もう一つ。これは経理担当者の方でも見落としがちな、組合カード特有の論点です。多くの組合では、利便性の高い請求書発行サービスや立替保証の対価として、毎月のETC利用料金に対して数パーセントの「事務手数料」がかかります。(※手数料率は組合により異なります)
組合に支払う「事務手数料」の会計処理
この事務手数料は、出資金とは異なり、返金されない純粋な「費用」です。そのため、ETC利用料本体とは別に、経費として計上する必要があります。勘定科目は「支払手数料」や「雑費」などが適当でしょう。
請求書に「事務手数料」の記載があった場合は、忘れずに費用計上してください。
【事務手数料の仕訳例】ETC利用料30,000円に対し、事務手数料が1,650円(税込)の場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 1,500 | 未払金 | 1,650 |
| 仮払消費税等 | 150 |
この事務手数料も、インボイス(請求書)に消費税額が記載されていれば、もちろん仕入税額控除の対象となります。



いかがでしたか。少し細かい話になりましたが、こうした細部を正確に処理することこそが、税務署からの信頼を得て、健全な経営の土台を築く上で非常に重要です。特に「出資金」の扱いは、あなたの帳簿の正確性を示す試金石とも言えます。ぜひ、この機会に正しい会計処理をマスターしてください。
【Q&A】経理担当者のよくある質問


さて、最後の仕上げとして、本編では触れきれなかったものの、私が顧問先からよく受ける質問について、Q&A形式で回答していきます。ここを押さえておけば、あなたのインボイス対応は、より盤石なものになるはずです。
Q1. 1万円未満の「少額特例」はETC料金にも適用されますか?
A1. はい、結論から言うと適用されます。これは「少額特例」と呼ばれる制度で、基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1億円以下の事業者などを対象に、税込み1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められる、というものです。ETC利用の場合、1回の走行料金が1万円未満であれば、この特例の対象となります。
【専門家の本音】特例への過度な依存は推奨しません
特例が使えるからといって、「じゃあ、インボイスは要らないか」と考えるのは、非常に危険なサインだと私は考えています。その理由は3つあります。
- 特例は「期間限定」の措置である:この少額特例は、現在のところ令和11年(2029年)9月30日までの経過措置とされています。恒久的な制度ではないため、いずれは原則通りの対応が求められます。
- 経理プロセスの複雑化を招く:「1万円以上はインボイス必須、未満は不要」といった二重基準は、経理のルールを複雑にし、かえってミスを誘発する原因になります。「すべての取引で証憑を得る」というシンプルなルールを徹底する方が、長期的にははるかに効率的です。
- 税務調査での心証が悪い:特例に安易に頼る姿勢は、税務調査官に「この会社は証憑管理の意識が低い」という印象を与えかねません。すべての取引で完璧な証憑を揃えておくことが、何よりの防御になります。
そもそも、この記事でご紹介している「請求書がインボイスになるカード」を使えば、特例を意識する必要すらありません。小手先のテクニックに頼るのではなく、根本的な仕組みで解決することをお勧めします。
Q2. 請求書データは「電子帳簿保存法」にどう対応すればいいですか?
A2. 非常に重要なご質問です。組合のウェブサイトからダウンロードした請求書のPDFデータは、電子帳簿保存法(以下、電帳法)における「電子取引データ」に該当します。そして、電帳法のルールにより、電子データとして受け取ったものは、原則として電子データのまま保存する義務があります。紙に印刷して保存するだけでは、法律の要件を満たさないため、注意が必要です。
電子取引データの保存要件と、最も簡単な対応策
電帳法では、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 真実性の確保:データが改ざんされていないことを担保する措置(例:タイムスタンプの付与、訂正削除の履歴が残るシステムへの保存など)。
- 可視性の確保:誰もが視認・確認できるようにしておく措置(例:「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておくこと)。
「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、最も簡単で確実な対応策があります。それは、お使いの会計ソフトが提供している「ファイル保存機能」や「証憑保管サービス」を活用することです。freeeやマネーフォワード、弥生会計といった主要な会計ソフトは、この電帳法に標準で対応しており、請求書データを取り込むだけで、これらの要件を自動的に満たしてくれます。これを使わない手はありません。
電帳法への対応を怠ると、最悪の場合、青色申告の承認が取り消されるといった重いペナルティのリスクもゼロではありません。必ず、ルールに則った方法でデータを保存してください。
Q3. レンタカーや従業員の自家用車で使った場合、インボイスはどうなりますか?
A3. これは、組合カードがその真価を最も発揮するポイントの一つですね。前述の通り、ETCコーポレートカードは、事前に登録した特定の車両でしか利用できず、割引も適用されません。
しかし、高速情報協同組合などが発行するカードは、車両を限定しません。そのため、出張先で借りたレンタカーでも、緊急で従業員の自家用車を業務利用した場合でも、問題なく利用できます。
そして最も重要なのは、どの車で利用したかにかかわらず、その利用分もすべて月締めの請求書(インボイス)にまとめて記載されるという点です。経理担当者としては、インボイスの心配を一切することなく、あらゆる車両でのETC利用を許可できるのです。これは、特に不特定の車両を利用する機会が多い、建設業、イベント業、あるいは全国に出張する機会の多い企業にとって、計り知れないほど大きなメリットと言えるでしょう。
未来へ!ペーパーレスで戦略的な経理部になるために


ここまで、ETC利用に関するインボイス制度の課題と、その具体的な解決策についてお話ししてきました。この記事でお伝えしたかったことは、単なる経費精算テクニックではありません。それは、時代遅れの非効率な作業からあなた自身を解放し、より創造的で戦略的な仕事に時間を使うための「未来への切符」です。
書類の山と格闘する時間は、もう終わりです。ペーパーレス化を実現し、自動化できる業務はどんどんシステムに任せていく。そうして生まれた時間で、資金繰りの改善策を考えたり、経営分析を行ったりする。それこそが、これからの経理担当者に求められる、本当の価値ではないでしょうか。この記事が、あなたがその一歩を踏み出すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
- インボイス制度ではクレジットカードの利用明細書は原則として認められない
- インボイスの要件を満たすためには6つの項目の記載が必要である
- 代替案である利用証明書は収集と管理に多大な手間がかかる
- 解決策は請求書自体がインボイス要件を満たす法人ETCカードを選ぶこと
- これにより従業員による書類集めが不要になり経理業務が劇的に効率化する
- 審査が厳しい法人カードに代わるのが高速情報協同組合などのカードである
- 組合カードは出資金制度により与信審査なしで発行が可能
- 設立間もない会社や個人事業主でも安心して申し込める
- もう一つの選択肢はNEXCO発行のETCコーポレートカードである
- 組合カードは車両不問で柔軟性が高く中小企業におすすめ
- コーポレートカードは割引率が高いが大企業向けと言える
- 組合カードの申し込みはウェブで完結し手続きは非常に簡単
- 会計処理の勘定科目は旅費交通費で問題ない
- 出資金は経費ではなく資産として計上する必要がある
- 少額特例や電子帳簿保存法など関連する法制度も理解しておくことが重要


