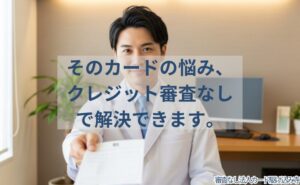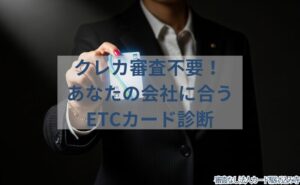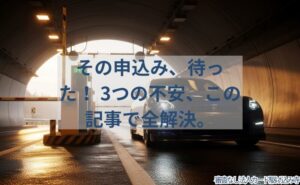この記事は約24分で読めます。
【比較】ETCコーポレートカードと協同組合の損益分岐点を解説
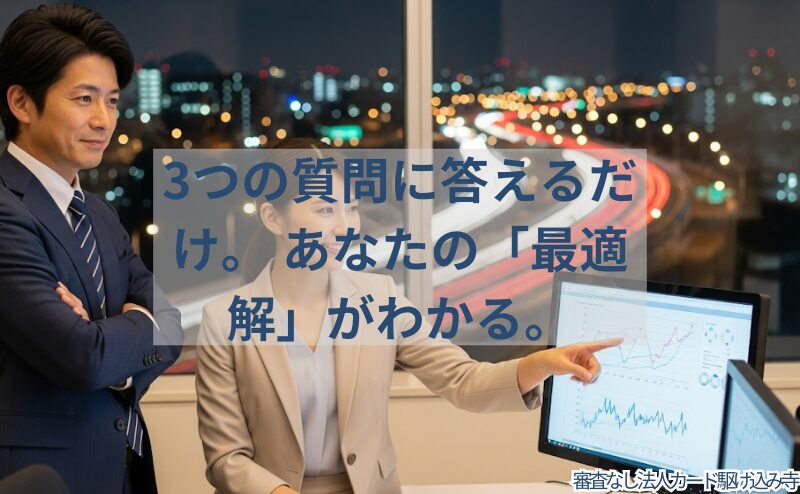
「ETCコーポレートカード」と「協同組合のカード」、一体どちらが自社にとって本当に得なのか?…もしあなたが今、そんな疑問を抱えているなら、安心してください。5年前の私も、PCの前で毎晩のように頭を抱え、まったく同じことで悩んでいました。
このETCコーポレートカードと協同組合の比較というテーマは、単純なようで本当に奥が深い。圧倒的な割引率というメリットに惹かれつつも、組合に支払う手数料の文字が重くのしかかる…。結局、自社にとっておすすめのETCコーポレートカード組合はどこなのか、答えが出ないまま時間だけが過ぎていく。あの焦りと不安は、今でも忘れられません。
この記事は、単なる情報の羅列ではありません。過去の私が喉から手が出るほど欲しかった「決断を下すための具体的な根拠」を、私の実体験のすべてを注ぎ込んで解説するものです。読み終える頃には、あなたの会社が次に取るべきアクションが、明確に見えていることをお約束します。
- ETCコーポレートカードと組合カードの根本的な違いがわかる
- 料金シミュレーションで、どちらが経費削減に繋がるか一目瞭然になる
- カード選びで多くの経営者が陥りがちな「3つの落とし穴」を回避できる
- あなたの会社の状況に合わせた、今取るべき最適なアクションが明確になる
【基礎知識】ETCコーポレートカードと協同組合を比較

そもそも何が違う?2大法人ETCカードの構造

こんにちは。『審査なし法人カード駆け込み寺』の駆け込みテンチョーです。
まず、本題に入る前に一つだけ質問させてください。あなたが今、法人向けのETCカードを探しているとして、その選択肢にどんなイメージを持っていますか?
5年前、40代でネットショップ事業を立ち上げたばかりの私は、「カード会社に申し込んで、審査に通れば手に入るもの」くらいにしか考えていませんでした。でも、現実はそんなに甘くなかった。設立間もない個人事業主というだけで、面白いように審査に落ち続けたんです。
そんな八方塞がりの状況で、ようやくたどり着いたのが「ETCコーポレートカード」と「協同組合が発行するETCカード」という2つの選択肢でした。この2つは、言ってみれば全く異なる思想で設計された、似て非なる存在です。この違いを最初に理解しておくことが、後悔しないカード選びの絶対的な第一歩になります。
ものすごく簡単に例えるなら、ETCコーポレートカードは「NEXCOという高速道路の”メーカー”が、ヘビーユーザー向けに直接提供するプロ仕様の割引制度」です。一方、協同組合のカードは「組合という”販売代理店”が、メーカーの製品をより多くの人が使えるように、独自のサービスを付加して提供してくれるパッケージ商品」といった感じでしょうか。
メーカー直販品は高性能(割引率が高い)だけど、購入条件(審査)が厳しい。一方、販売代理店経由のものは、誰でも手に入れやすいように条件が緩和されている、というわけです。この根本的な違いが、なぜ生まれるのか。実は、そこには「信用リスクを誰が負うか」という、ビジネスの核心が隠されています。
専門家の視点:なぜ審査基準と割引体系が違うのか?
経理や財務の視点で見ると、この2つのカードの違いは「信用供与の主体」に集約されます。
- ETCコーポレートカード:NEXCOが直接、利用者(あなたの会社)の信用力を審査します。過去の財務状況などから「この会社はきちんと支払いをしてくれるか」を厳しく判断するため、設立間もない企業にはハードルが高くなります。その代わり、信用のおける相手と認めたからこそ、強力な割引を提供できるのです。
- 協同組合のカード:協同組合が、いわば「保証人」のような役割を果たします。組合がNEXCOに対して支払いを保証するため、個々の利用者の審査が原則不要になります。その保証の対価として、私たちは組合に出資金を預け、走行料金に応じた事務手数料を支払う、というビジネスモデルなわけですね。
この構造を理解すると、なぜ片方が厳しく、もう片方が手軽なのかが、スッと腑に落ちると思います。
それでは、この構造的な違いが、具体的にどのような特徴として現れるのか。次の比較表で、客観的な事実を整理してみましょう。
| 項目 | ETCコーポレートカード | 協同組合のETCカード |
|---|---|---|
| 発行元(契約先) | NEXCO東/中/西日本 | 各事業協同組合 |
| 主な対象者 | 設立年数が長く、財務状況が安定している法人 | 設立間もない法人、個人事業主、審査に不安がある事業者 |
| 割引制度の根幹 | 大口・多頻度割引(車両単位) | NEXCOの各種割引(休日、深夜など)+組合独自のサービス |
| 与信審査 | あり(決算書等の提出が必須) | 原則なし(組合への加入が出資・信用の証明となる) |
もちろん、これはあくまで基本的な構造の話です。実際には、それぞれのカードに細かいメリットやデメリットが存在します。次の項目で、もっと具体的に両者を比較していきましょう。
メリット・デメリットを一覧で比較

さて、基本的な構造の違いが分かったところで、今度はもっと具体的に、それぞれのカードが持つメリットとデメリットを比較検討してみましょう。
ここは経営者として、シビアな目で判断すべきポイントです。私の経験上、どちらか一方が絶対的に優れている、ということはありません。言ってしまえば、事業の状況に応じて「どちらのメリットを最大限に享受し、どちらのデメリットを許容できるか」というトレードオフの関係にあるのです。
例えば、5年前の私。創業期の私にとって、最優先事項は何よりも「カードが手に入ること」そのものでした。売上も信用もない。だけど、事業のためには車を走らせなければならない。この状況で、審査がないというメリットは、他のどんなデメリット(例えば将来的に支払う手数料)にも勝る絶対的な価値があったのです。一方で、事業が軌道に乗り、毎月の高速利用額が数十万円規模になってくると、今度は「割引率」というメリットが会社の利益に直結する、非常に重要な要素へと変わっていきます。
このように、メリットとデメリットの価値は、あなたの会社のステージによって変化します。まずは下の表で、客観的な事実を冷静に比較してみてください。
| ETCコーポレートカード | 協同組合のETCカード | |
|---|---|---|
| ● メリット | 大口・多頻度割引による圧倒的な割引率(最大40%) NEXCOとの直接契約という社会的信用性 組合手数料などが一切かからない明朗会計 | 設立1年未満や個人事業主でも発行可能 信用情報に影響しない(クレジット機能なし) 必要枚数を柔軟に発行しやすい |
| ● デメリット | 申し込みのハードルが高い(原則2期以上の決算書が必要) 保証金(最低10万円~)による資金の固定化 カード発行までに1ヶ月以上かかる場合がある | 大口・多頻度割引が適用されない 組合への出資金(1万円)が必要(※脱退時返金) 走行料金に対して組合の事務手数料がかかる |
 筆者
筆者まぁ、正直なところ、創業当初の私にはETCコーポレートカードという選択肢は現実的ではありませんでした。審査以前に、保証金の10万円という数字が重くのしかかったんです。当時の私にとって10万円は、商品の仕入れ代金であり、サイトの広告費でした。事業を成長させるための運転資金を、ただ眠らせておかなければならない。この心理的なプレッシャーは、経験した者にしか分からないかもしれません。組合のカードがなければ、あの資金繰りの厳しい時期を乗り越えられなかったでしょうね。
いかがでしょうか。メリットとデメリットは表裏一体です。あなたの会社が今、どのステージにいて、何に一番の価値を置くのか。そこを冷静に見極めることが、後悔しないカード選びの第一歩になります。
当時の私と、同じように悩んでいるあなたへ
「ウチの会社でも、本当にカードが作れるだろうか…」もしあなたが今、そんな不安を抱えているなら、まずは第一歩として、私が最終的に選んだ組合の公式サイトを覗いてみてください。必要な書類や手続きの流れが具体的に分かるだけでも、心の負担は軽くなるはずです。
▼私が実際に比較検討した、信頼できる組合はこちら▼
コーポレートカード割引の計算方法とは?


ここで、ETCコーポレートカードの最大の魅力であり、同時に多くの経営者を悩ませる「大口・多頻度割引」について、もう少しだけ詳しく、そして実践的に解説させてください。
「最大40%割引」という言葉は、広告などで見るとものすごく魅力的に感じますよね。実際、そのポテンシャルは本物なのですが、この割引制度、ちょっとだけ仕組みが複雑なんです。何を隠そう、私も最初は「利用額の40%が単純に引かれるのか?」と勘違いしていました。
この割引は、「車両1台ごとの月間利用額」に応じて、割引率が段階的に上がっていく仕組みになっています。これは、たくさん使ってくれる優良顧客をNEXCOが優遇するための、合理的な制度設計と言えますね。(参照:NEXCO中日本公式サイト 大口・多頻度割引)
大口・多頻度割引の仕組み(ETC2.0搭載車の場合)
- 月の利用額のうち、5,000円超~10,000円以下の部分:20%割引
- 月の利用額のうち、10,000円超~30,000円以下の部分:30%割引
- 月の利用額のうち、30,000円を超える部分:40%割引
※NEXCO公式サイトによると、ETC2.0を搭載していない車両は、上記割引率がそれぞれ10%、20%、30%になるとされています。
言葉だけだと少し分かりにくいので、具体的な例で見てみましょう。例えば、営業車1台が1ヶ月に50,000円の高速道路を利用したとします。
【計算例:月50,000円利用した場合】
- 最初の5,000円:割引なし(0円)
- 次の5,000円(5,001円~10,000円):5,000円 × 20% = 1,000円割引
- 次の20,000円(10,01円~30,000円):20,000円 × 30% = 6,000円割引
- 残りの20,000円(30,001円~50,000円):20,000円 × 40% = 8,000円割引
つまり、合計の割引額は 1,000 + 6,000 + 8,000 = 15,000円となります。50,000円の利用に対して15,000円の割引なので、この場合の実質的な割引率は30%ですね。このように、利用すればするほど、全体の割引率も上がっていく仕組みです。
よくある誤解:「会社の合計利用額」ではありません
ここで絶対に間違えてはいけないのが、この割引は会社の車両全体の合計利用額ではなく、あくまで「車両1台ごと」に計算されるという点です。例えば、2台の車がそれぞれ25,000円ずつ利用した場合(合計50,000円)、それぞれの車で割引が計算されるため、合計の割引額は先ほどの1台で50,000円利用したケースよりも少なくなります。この仕様を理解していないと、想定していたほどの割引額にならず、資金計画が狂ってしまう可能性もあります。
経理担当者・経営者の方へ:稟議書への活用法
この段階的な割引計算は、経費削減効果を社内で説明する際に非常に有効なデータとなります。例えば、コスト削減のための稟議書を作成する際には、単に「最大40%割引」と書くのではなく、「現状の平均利用額である月額〇〇円の場合、実質割引率は△△%となり、年間□□円の経費削減が見込まれます」というように、具体的なシミュレーション結果を提示することで、説得力が格段に増します。このページの計算式は、そのための強力な武器になるはずです。
高速情報協同組合とETC協同組合とは


さて、ここまでETCコーポレートカードと協同組合カードという大きな枠で比較してきましたが、「協同組合」という選択肢に絞った時、次に考えるべきは「では、具体的にどの組合を選ぶか?」という点です。
実際には全国に数多くの組合が存在しますが、ここでは多くの事業者に利用され、私自身も当時徹底的に比較検討した代表的な組合として、「高速情報協同組合」と「ETC協同組合」の2つを具体的に見ていきましょう。
私自身、創業期にお世話になったのは、このうちの一つです。どちらの組合も、設立間もない法人や個人事業主の強い味方になってくれるという点では共通していますが、実は細かい手数料や設立背景に違いがあり、これが後々の選択を左右することもあります。
2つの代表的な協同組合の比較表
| 項目 | 高速情報協同組合 | ETC協同組合 |
|---|---|---|
| 出資金 | 10,000円(脱退時返金) | |
| カード発行手数料 | 550円 / 1枚(税込) | 880円 / 1枚(税込) |
| 年間手数料 | 550円 / 1枚(税込) | 880円 / 1枚(税込) |
| 事務手数料 | 走行料金に対して8% | |
| 設立年 | 1993年(平成5年) | 公式情報なし |
| 認可省庁 | 内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働省など多数 | 公式情報なし |
このように客観的なデータで比較すると、いくつかの重要なポイントが見えてきます。まず、事業運営の根幹に関わる事務手数料は8%で同じです。出資金も同額。そうなると、差がつくのはカード1枚ごとにかかる発行手数料と年間手数料ですね。
1台あたりの年間コストは、高速情報協同組合が1,100円、ETC協同組合が1,760円。差額は660円です。もし、車両を10台、20台と多く抱える運送業の経営者であれば、このランニングコストの差は決して無視できない金額になってくるでしょう。



一方で、これから事業を始める、あるいは始めたばかりの創業者の視点で見ると、少し違った解釈もできます。ETC協同組合は、公式サイトで「個人事業を始めたばかりの方は開業届、取引先との契約書、領収書など」というように、設立直後の事業者が用意しにくい確定申告書以外の書類での申し込みにも言及しています。このあたりは、数字には表れない「柔軟性」や「懐の深さ」と言えるかもしれませんね。
テンチョーの私見:では、どう判断するか?
もし私が今の知識を持ったまま5年前に戻って、どちらか一方を選ぶとしたら、以下のように考えるでしょう。
- 判断基準① 合理性とコスト重視なら:
既に複数台の車両が稼働しており、1円でもランニングコストを抑えたい、というコスト意識の高い経営者の方。また、30年近い運営実績という信頼性を重視するなら、手数料が安く、歴史のある「高速情報協同組合」が合理的な選択肢になる感じがします。 - 判断基準② 柔軟性とスピード重視なら:
まだ会社を設立して数ヶ月しか経っておらず、提出できる書類も限られている。とにかく「まず一枚、確実にカードを手に入れる」ことを最優先したい創業者の方。そういった方には、柔軟な申し込み対応が期待できる「ETC協同組合」が心強い味方になってくれるかもしれません。
私の見解が、あなたの判断の一助となれば幸いです。最終的な決断を下すために、公式サイトで最新の情報を確認し、ご自身の目で比較検討してみてください。
【実践比較】あなたの会社に合うカードの選び方


- テンチョーが語る!組合選び3つの落とし穴
- 【料金シミュレーション】組合の手数料は本当に損か?
- 乗り換えの具体的な手順とタイミング
- 結論!今選ぶべきおすすめ組合と次のステップ
- 【まとめ】ETCコーポレートカードと協同組合の比較
テンチョーが語る!組合選び3つの落とし穴
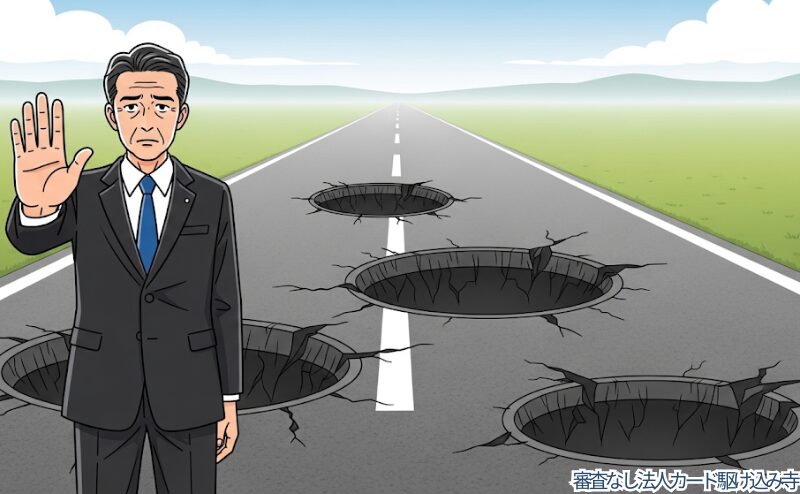
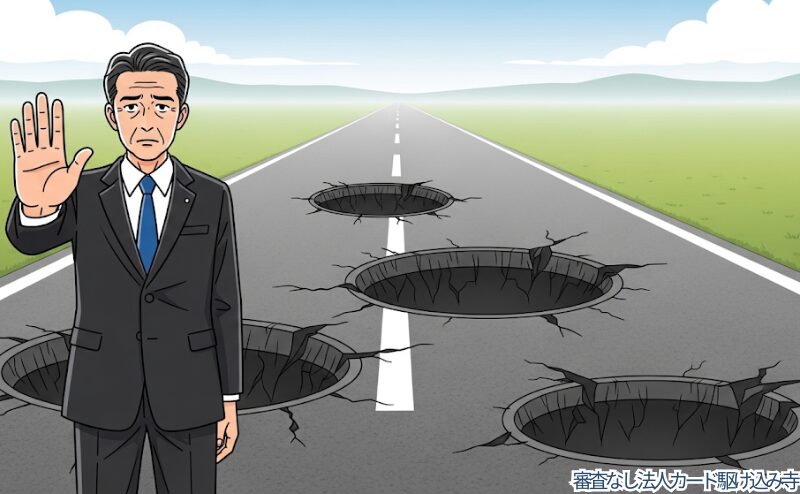
さて、ここからはより実践的な話に入っていきましょう。特に、これから初めて法人ETCカードを持つ、創業して間もない経営者の方や、とにかく失敗しない選択をしたい慎重な方に向けて、私の経験から「これだけは気をつけてほしい!」と心から思うポイントを3つ、包み隠さずお話しします。言ってしまえば、これは5年前の私が実際にハマりかけた「落とし穴」です。この知識があるかないかで、数年後のあなたの会社のキャッシュフローや業務効率が、本当に変わってくるかもしれません。
落とし穴①:手数料の安さだけで選んでしまう
経営者たるもの、手数料は1円でも安い方がいいに決まっています。これは事業を運営する上での絶対的な正義ですし、私も最初はそう考えていました。複数の組合の資料を取り寄せては、電卓を片手に手数料率を比較する毎日でしたからね。
しかし、目先の数字だけに囚われてしまうと、もっと大切な「運用コスト」という視点を見失う可能性があります。
例えば、事務手数料が他より1%安い組合があったとします。これは非常に魅力的ですよね。しかし、もし、その組合の請求書の締め日や支払いサイトが自社のキャッシュフローサイクルと微妙にズレていたらどうでしょう?あるいは、毎月送られてくる利用明細が非常に分かりにくいフォーマットで、経理担当者が内容をExcelに転記し直すのに毎月2時間も余計な時間がかかってしまったら?
時給2,000円のスタッフなら、それだけで毎月4,000円の人件費がかかります。果たして本当に「安い」と言えるでしょうか。安さというメリット以上に、業務上のデメリットが大きくなってしまう可能性も十分にあるのです。
手数料の比較はもちろん重要です。ですが、それだけで即決するのは少し危険な感じがします。
【テンチョーからの実践的アドバイス】
申し込みを検討している組合の公式サイトで、「請求・支払いサイクル」と「利用明細のサンプル」が公開されているか必ず確認してください。もし情報がなければ、ためらわずに電話で問い合わせてみましょう。その一手間が、将来の大きな時間的コストを防ぎます。
落とし穴②:サポート体制の確認を怠る
これは、私が実際に経験したことなのですが、独立して1年ほど経ったある日、送られてきた利用明細の金額に、どうしても納得がいかない点があったのです。記憶にある利用履歴と、請求額が数千円ほどズレている。たかが数千円、されど数千円です。会社の金を1円たりとも無駄にはできません。
少し緊張しながら組合のサポートデスクに電話したところ、電話口の担当者の方が私の拙い説明を辛抱強く聞いてくれて、最終的にはこちらの勘違いだったことが判明しました。恥ずかしい話ですが、その時の丁寧で迅速な対応に、私は心底ホッとしたのを今でも覚えています。この経験から、「何かあった時に、ちゃんと相談できる相手がいる」という安心感は、数字には表れない非常に大きな価値だと痛感しました。



もし、この時の対応が悪かったり、電話がなかなかつながらなかったりしたら、私はきっと大きなストレスを感じ、本業に集中できなかったでしょう。組合は、一度加入すると長い付き合いになる、いわば事業のパートナーです。申し込みの前に、一度電話で簡単な質問をしてみて、その組合の「人となり」や「雰囲気」を感じてみるのも、失敗しないための重要なステップだと思います。
特に初めて法人カードを作る方は、分からないことだらけのはず。そんな時に気軽に相談できる窓口があるかどうかは、組合選びの重要な判断基準にすべきです。
落とし穴③:将来の乗り換えを想定していない
協同組合のカードは、創業期の事業者にとって、まさに「駆け込み寺」のような、なくてはならない存在です。これは間違いありません。
しかし、あなたの事業が成長し、会社の信用力が高まり、高速道路の利用額が増えてきたら…。いつかは、より割引率の高いETCコーポレートカードへの「卒業」を考える時が来ます。これは、事業が順調に育っている証であり、非常に喜ばしいステップです。
私が組合を選んだとき、常に頭の片隅にあったのはこの「卒業」の二文字でした。つまり、組合はあくまで事業を安定させるまでお世話になる「学び舎」であり、最終目標はNEXCOと直接契約する「プロの世界」だと考えていたのです。
この視点を持つと、組合選びの基準も少し変わってきます。
出口戦略から考える組合選び
将来の乗り換え(脱退)をスムーズに行うためには、やはり多くの企業が利用していて、実績のある大手の組合を選ぶ方が安心感があります。公式サイトに脱退手続きや出資金の返還プロセスが明記されているかは、必ずチェックすべき項目です。これが不明瞭な組合は、少し注意が必要かもしれません。
今すぐの話ではないかもしれませんが、自社が成長した2〜3年後の未来を想像しながら組合を選ぶと、より後悔のない、戦略的な選択ができるはずです。
【料金シミュレーション】組合の手数料は本当に損か?


さて、ここからはこの記事の核心とも言える、お金の話をしましょう。
「組合の事務手数料8%って、やっぱり高いんじゃないの?」
「コーポレートカードの割引と比べて、結局どっちが得なの?」
この疑問は、私も当時に何度も自問自答した、非常に重要なテーマです。特に、すでに事業が軌道に乗り、毎月の高速利用額が増えている経営者の方にとっては、この一点に答えを求めてこの記事を読んでくださっているのかもしれません。
先に結論から言うと、これは単純な二者択一の問題ではありません。なぜなら、私たちは表面的な割引率だけでなく、「目に見えないコスト」も天秤にかける必要があるからです。
経営者の視点:「保証金の機会損失」というコスト
ここで、特にキャッシュフローを重視する経営者の方に考えていただきたいのが、ETCコーポレートカードに必要な「保証金」の存在です。最低10万円というこのお金は、組合の出資金と違って解約するまで戻ってきません。つまり、会社の運転資金から少なくとも10万円が固定化され、そのお金が生み出すはずだった未来の利益(=機会損失)を失っている、と考えることもできるのです。
例えば、その10万円を広告費に投下していれば、いくらの売上が生まれたでしょうか?新しい機材を導入していれば、どれだけ生産性が上がったでしょうか?
この「機会損失」というコストは、会社のステージや資金状況によって大きく変動するため、一概に金額では表せません。しかし、割引率のシミュレーションを見る際には、常にこの「目に見えないコスト」の存在を頭の片隅に置いておく必要があります。
それでは、上記の視点を踏まえた上で、まずは純粋な支払額がどう変わるのか、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。これがあなたの意思決定の土台となります。
【シミュレーション条件】
- ETCコーポレートカード:大口・多頻度割引(ETC2.0)を適用。
- 協同組合カード:NEXCOの各種割引(休日・深夜等)も適用されますが、ここでは公平性を期すため、それらの割引は考慮せず、走行料金に事務手数料8%を加算した金額で算出。
- 注意点:この計算には、前述の「保証金の機会損失」は含まれていません。
| 車両1台の 月間利用額 | ETCコーポレートカードの 支払額(割引後) | 協同組合カードの 支払額(手数料後) | 月間の差額 (組合カードが高い分) |
|---|---|---|---|
| 30,000円 | 26,500円 (割引額 3,500円) | 32,400円 (手数料 2,400円) | +5,900円 |
| 50,000円 | 35,000円 (割引額 15,000円) | 54,000円 (手数料 4,000円) | +19,000円 |
| 100,000円 | 67,000円 (割引額 33,000円) | 108,000円 (手数料 8,000円) | +41,000円 |
| 300,000円 | 187,000円 (割引額 113,000円) | 324,000円 (手数料 24,000円) | +137,000円 |
この数字を見ると、身も蓋もない結論ですが、純粋な支払額だけで言えば、月の利用額が1万円を超えるあたりからETCコーポレートカードの方が圧倒的に有利です。特に利用額が数十万円規模になる運送業などでは、組合カードの手数料が年間でとんでもない金額になることが分かりますね。これが「卒業」を考えるべき理由です。



「じゃあ、やっぱり組合は損じゃないか!」と思うかもしれません。しかし、思い出してください。このシミュレーションは、ETCコーポレートカードの審査に通る、という大前提に立っています。創業期の私のように、そもそもスタートラインに立てない事業者にとっては、組合カードの手数料は、事業を前に進めるために支払うべき、いわば「時間を買うための投資」とも言えるのです。
乗り換えの具体的な手順とタイミング


事業が軌道に乗り、毎月の高速利用額も安定してきた。そして何より、提出できる決算書の内容も良くなってきた。…そうなれば、いよいよお世話になった協同組合からの「卒業」、つまりETCコーポレートカードへの乗り換えを検討するステージです。
ただ、こう考える経営者の方も少なくないはずです。「乗り換えって、手続きが面倒なんじゃないか?」「もしNEXCOの審査に落ちたら、今の組合にも居づらくなるし…」と。私もそうでした。現状維持は楽ですが、会社の利益を1円でも多く残すためには、このステップを避けては通れません。安心してください。これからお話しする手順とポイントさえ押さえれば、驚くほどスムーズに移行が可能です。
これが乗り換えの全手順!私の実践プレイブック
- 【準備】NEXCOへの申し込みと審査書類の収集
まずは、自社の所在地を管轄するNEXCOのウェブサイトから、ETCコーポレートカードの申込書を入手します。同時に、必要書類(発行3ヶ月以内の登記簿謄本や直近2期分の決算書など)を準備しましょう。ここが最初の関門ですね。 - 【申請】書類の提出と審査
準備した書類をNEXCOに提出します。審査期間はNEXCOによると通常1ヶ月程度とされていますが、余裕を見ておきましょう。この間、私たちはただ結果を待つだけです。 - 【承認】保証金の支払いとカード発行
無事に審査を通過すると、書面で通知が来ます。その後、指定された口座に保証金(月の利用見込み額の4倍、最低10万円)を振り込むと、いよいよカードが発行され、会社に郵送されてきます。 - 【最重要】新しいカードの利用開始 → その後に組合へ連絡
ETCコーポレートカードが手元に届いたら、すぐに車両で利用を開始できます。そしてここが一番重要です。新しいカードが問題なく使えることを確認してから、今までお世話になった協同組合に連絡し、脱退の手続きを進めます。 - 【完了】古いカードの返却と出資金の返還
組合の指示に従い、古いカードを返却します。最後の利用料金の精算が終われば、預けていた出資金(1万円)が指定の口座に返還されて、すべて完了です。
絶対にやってはいけないこと
絶対に、新しいコーポレートカードが届く前に、現在利用している組合のカードを解約しないでください。
万が一、コーポレートカードの審査に落ちてしまった場合や、発行が想定より遅れた場合に、高速道路で割引を受けられるカードが一時的になくなってしまいます。これは事業にとって大きな損失です。必ず「保険」として、組合のカードは手元に置いておきましょう。



私個人の意見としては、乗り換えのベストタイミングは、決算で良い数字が出た直後の1〜2ヶ月間だと考えています。審査で提出する決算書の内容が良いほど、審査担当者の心証も良くなるはずですからね。事業年度の終わりが見えてきたら、「来期は乗り換えるぞ」と計画を立てて、準備を始めるのが最もスマートなやり方だと思います。
結論!今選ぶべきおすすめ組合と次のステップ


さて、ここまで様々な角度から2種類のカードを比較してきました。最後に、ここまでの話をすべて踏まえて、「あなたの会社は、今どちらの道に進むべきか」という問いに対する、駆け込みテンチョーとしての最終的な「処方箋」を提示したいと思います。
これは、私がもしあなたの会社の状況だったらどう判断するだろうか、と考え抜いた末の結論です。ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
【最適カード診断】3つの質問であなたの現在地を知る
まず、あなたの会社の状況を客観的に把握するために、以下の3つの質問に「はい」か「いいえ」で答えてみてください。
- 設立してから2年以上が経過していますか?
- 直近2期連続で黒字決算を達成していますか?
- 車両1台あたりの月間高速利用額が、平均して3万円を超えていますか?
…いかがでしたでしょうか。この3つの質問は、NEXCOがETCコーポレートカードの審査で重視すると言われる項目に基づいています。あなたの答えによって、進むべき道は明確になります。
診断結果①:3つの質問すべてに「はい」と答えた経営者の方へ
もしあなたが3つの質問すべてに「はい」と答えられたなら、今すぐ「ETCコーポレートカードへの乗り換え」を本格的に検討すべきです。
シミュレーションで見た通り、あなたの会社の利用状況では、既に組合に支払っている手数料が、コーポレートカードの割引額を大きく上回っている可能性が極めて高いでしょう。現状維持は、毎月確実に会社の利益を流出させている状態と言っても過言ではありません。
「保証金が…」とためらう気持ちは痛いほど分かります。しかし、例えば毎月の差額が5万円だったとすれば、わずか2ヶ月で10万円の保証金は回収できる計算です。長期的に見れば、乗り換えないという選択肢はないはずです。
【あなたの次のステップ】
- 直近2期分の決算書と登記簿謄本を準備する。
- NEXCOの公式サイトから申込書をダウンロードし、必要事項を記入する。
- すぐにNEXCOへ申し込みを行う。
診断結果②:3つの質問に1つでも「いいえ」があった経営者の方へ
もしあなたが1つでも「いいえ」と答えたなら、現時点での最適な選択肢は「協同組合のETCカード」です。
特に、会社を設立して間もない、あるいはこれから設立するという創業者の方にとって、ETCコーポレートカードの高い割引率は、まだ「高嶺の花」かもしれません。今は、審査のハードルを越えようと苦心するよりも、まずは事業の基盤を固めることが最優先。審査がなく、確実に事業用のETCカードを手に入れられる組合のカードは、あなたの事業を力強くサポートしてくれる最高のパートナーになります。
その上で、どの組合を選ぶべきか。これはあなたの会社の個性によって決まります。
【おすすめ組合とあなたの次のステップ】
- 少しでも固定費を抑えたい、合理性を重視するなら…
→ 高速情報協同組合(発行・年間手数料が安い)がおすすめです。
次のステップ:公式サイトからすぐに資料請求、または申し込みを行いましょう。
- 設立直後で書類に不安がある、柔軟性を重視するなら…
→ ETC協同組合(柔軟な申し込み対応が期待できる)が心強いでしょう。
次のステップ:まずは公式サイトを確認し、必要であれば電話で相談してみましょう。



カード一枚で、会社のキャッシュフローと経営者の心の余裕は大きく変わります。私の経験が、あなたの会社が次のステージへ進むための、小さなきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。悩んでいる時間が一番もったいないですよ!
【まとめ】ETCコーポレートカードと協同組合の比較
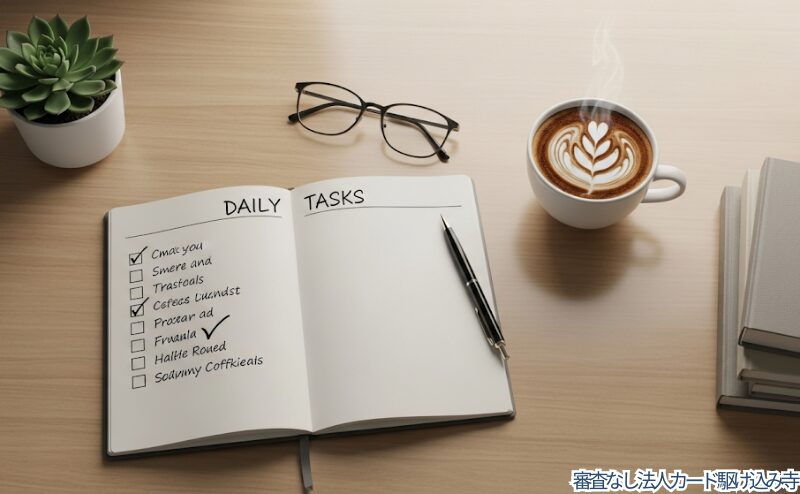
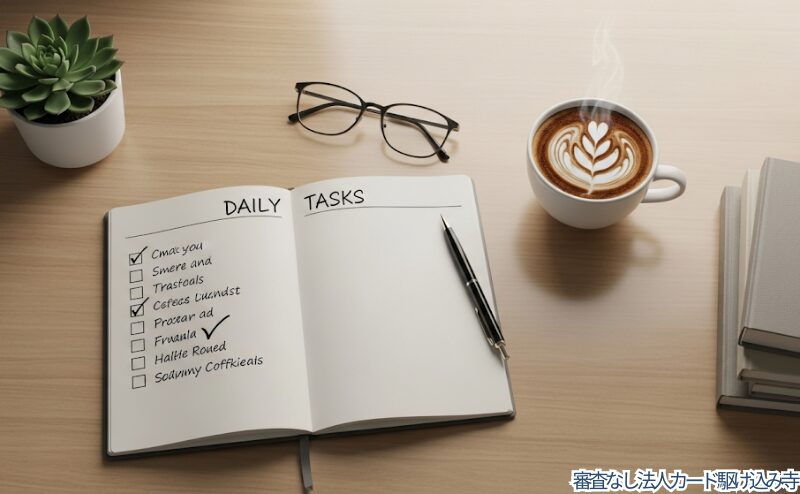
- 法人向けETCカードには大きく分けて2種類ある
- NEXCOが直接発行するETCコーポレートカード
- 事業協同組合が発行するETCカード
- コーポレートカードは割引率が非常に高いのが最大のメリット
- 大口・多頻度割引で最大40%の割引が適用される
- ただし申し込みには審査があり、ハードルは高い
- 保証金として最低10万円程度が必要になる
- 協同組合のカードは審査が原則ないのが最大のメリット
- 設立間もない法人や個人事業主でも発行できる
- ただし走行料金に対して組合の事務手数料がかかる
- 代表的な組合の手数料は8%程度が相場
- 組合への加入には出資金として1万円が必要(脱退時返金)
- 会社の状況やステージによって最適なカードは異なる
- 設立2年未満なら協同組合のカードが現実的な選択肢
- 事業が軌道に乗り利用額が増えたらコーポレートカードへの乗り換えを検討すべき
- 乗り換えは新しいカードが届いてから古いカードを解約するのが鉄則